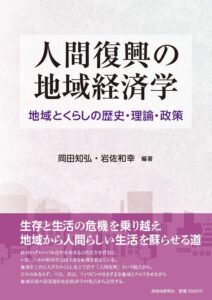はじめに
国立社会保障・人口問題研究所(以下「国立人口研」)は、2012年1月に人口動態に関する長期予測を公表した。それによると我が国の人口(現在1億2700万人)は、今後、長期にわたって急速なテンポで減少し、平成38年に1憶2000万人をきり、平成60年には1億人を下回る」と推計している。「人口減少時代」の到来は、この国のかたち、住民の暮らしや経済、地域、自治体のあり方にも大きな影響を及ぼす。このことにどう向き合い、どのような視点、方向、方針で問題を解決し、地域の再生、展望をきり拓いていくのか、その内実が鋭く問われている。
現在、各自治体は2015年度中に地方版人口ビジョンおよび総合戦略を策定するため、急ピッチで作業を進めている。政府の発表によれば、今年10月末までの策定状況は、都道府県が36団体(81%)、市区町村が773団体(44%)となっている。
ここではこうした状況を踏まえ、改めて政府の「地方創生」構想を時系列的に分析し、その論点、課題を明らかにし、今後の取り組みの方向を考えていきたい。なお、「各自治体における地方版人口ビジョンおよび総合戦略の策定状況と検討内容、課題」については、別にホームページに改訂版を掲載しており、併せてお読みいただきたい。
1.人口減少社会をどう捉えるのか
長期予測に基づく地域の姿について、西尾勝氏(東京大学名誉教授)は「核家族がいわば『核分裂』したかのような離散家族の形態が一般化した単身世帯・二人世帯の比率が急増する。その結果として、世帯数の減少は人口の減少ほどには急速でなく、過疎町村では空き家が増え、いわば「散村集落」のように、単身世帯・二人世帯といった小世帯が疎らに点在している姿になる」(地方議会人2013年9月号)と述べている。また、若い世代を中心に今後も大都市圏への人口流出が続き、地域の活力の低下が懸念されている。
三大都市圏でも「これまで地方圏に比べて高齢化の進行が緩やかであったが、団塊の世代を中心に今後急速に高齢化が進行し、高齢者医療、介護や生活保護などの行政需要が急増することへの対応や独居老人、老老介護の問題など、家族やコミュニティの機能の低下への対応が緊急に必要になる」(第30次地方制度調査会答申)と指摘されている。人口減少、少子高齢化、地域の再確立は、大都市圏においても喫緊の課題となる。もとより「大都市はひとり大都市のみで存立できるものではない。他の基礎自治体と相互依存することで成り立っており」(同答申)、大都市・地方間の実効ある連携は今後の重要な課題になる。
人口減少は、日本全体で見れば出生率の低下(自然減)、少子化が基本問題であり、地域間で見れば大都市圏、特に東京圏への一極集中と地方の転出超過(社会減)が重要な課題になる。現在の人口構成と出生数、死亡数の推移をみれば、今後、抜本的な少子化対策をとり、出生率が2.0程度までに回復したとしても人口減少は避けられない。子育て世代の核となる30代をみても、現在の人口は896万人であるが、2040年(30年後)には今の0~9歳人口531万人が30代となり、365万人以上減少する。移民政策を取らない限りこの現実は変わらない。
また、社会移動の状況を見ても、若年男女が集中する東京は、全国で最も低い出生率の都市であり、人口減少に拍車をかけている。その根底には暮らしや雇用、人間性の破壊があり、将来展望が描けない状況がある。その改善に本気で取り組まない限り実効ある人口減少対策にはならない。
同時に、人口減少社会をマイナス面だけで捉えず、それを都市のゆとり、安全性、環境との共生など質的な転換に繋げていくという視点が重要である。特に日本の都市は欧米に比べて過密であり、災害に強い都市計画、まちづくりは緊急の課題である。地震の問題1つとっても、中央防災会議の資料によれば、首都直下大地震、南海トラフ巨大地震の発生確率は30年以内に70%(東海地震は88%)以上と逼迫しており、猶予は許されない。
2.「自治体消滅」論を検証する
こうした中、増田氏+日本創成会議は、雑誌「中央公論」の2013年12月号で「2040年、地方消滅。『極点社会』が到来する」と題して「自治体消滅」論を展開した。「中央公論」が打ち出したタイトルは、「壊死する地方都市」(2013年12月号)、「消滅する市町村523全リスト」(2014年6月号)、「全ての町は救えない」(同7月号)という、極めて露骨なものである。
その論旨は、20歳から39歳までの若年女性人口が2010年から2040年までの30年間で半減以上になる自治体を一方的に「消滅可能性都市」と定義し、全国で896の自治体名を名指しで公表した。発表後、マスコミの大宣伝もあり、当該の自治体、住民、議員の間では不安や危惧、動揺が広がり、2014年6月議会で質問が集中した自治体もある。これは厳しい環境の中で努力している自治体や住民、議員等の努力や活動を否定し、意図的、戦略的に地域を切り捨てる“棄民政策”であり、新たな自治体再編、道州制導入に道を拓く攻撃と言える。
しかし、自治体はそう簡単には消滅しない。大森彌氏(東京大学名誉教授)は「起こるとすれば、自治体消滅という最悪の事態を想定したがゆえに、人々の気持ちが萎えてしまい、そのすきに乗じて『撤退』を不可避だと思わせ、人為的に市町村を消滅させようとする動きが出てくる場合である」(「町村週報」2014/5/19「自治体消滅の罠」)と指摘している。地域活性化センターの椎川理事長も「自治体は合併でしか消滅しない」(全国市長会2015/4/8)と述べている。
(1)「自治体消滅」論の前提条件、論旨は妥当か
このことについては、すでに多くの学者、研究者が論じており、その指摘に尽きる。ここでは藤山浩氏(島根県中山間地域研究C研究統括監)らの論点を紹介し、その妥当性を検証してみたい。
1つは、若年女性の「半減(以上)」でなぜ自治体は消滅なのか、消滅などしない。人口は減少するが、そこには現実に老若男女が住み、暮らし、生業を営んでいる。
2つ目は、小規模町村がなぜ消滅なのか、小規模性にこそ人口復元、地域再生の可能性がある。実際に様々な施策を講じて、「消滅する」と名指しされた1万人以下の町村でも人口を維持、あるいは増やし、地域が活性化している自治体もある。
3つ目は、推計のデータは2010年の国勢調査までのものであり、2011年以降のU&Iターンの増加等を反映していない。また、田園回帰の傾向、定住効果に対する過小評価がある。
4つ目は、今後とも首都圏への人口集中が収束せず、地方圏の人口減少は持続するとしているが、
この傾向にも変化がみられる。人口減少が早くから顕在化した中国地方、例えば島根県では社会減が年々減少している。
(2)田園回帰の流れも鮮明に
内閣府が2014年8月に公表した「農山漁村に関する世論調査」でも、田園回帰の方向が明確に示されている。都市部に住む人のうち「農山漁村に定住したい」と答えたのは31%で、2005年に実施した同様の調査と比べて11%も上昇した。年代別では20~29歳が38%と最も高く、若者層の間で田舎の暮らしに憧れる風潮が高まっている。定住実現に必要な条件(複数回答)では「医療機関の存在」が68%でトップ、「生活が維持できる仕事がある」が61%と続き、受け入れ側の課題が改めて浮き彫りになっている(日本経済新聞2014/8/9)。この田園回帰の根っこには、単なる「憧れ」だけでなく、新自由主義的グローバリズムがもたらす暮らしや雇用、人間性の破壊に対する批判、対抗が見てとれる。それは3.11東日本大震災を経験する中で模索された、自然と共生し人間らしい暮らし、持続可能な地域づくりへの思いと連動している。
また、総務省が今年9月に公表した「地域おこし協力隊」参加者の定住調査結果を見ても、制度が始まった2009年度から2014年度末までに協力隊員の任期が終了した945人(約3割が女性、20~30代が約8割)のうち、557人(59%)が同じ地域に住み続けている。活動した市町村にそのまま定住した443人のうち76人が起業、210人が就業、79人が就農している。総務省は隊員の定住・定着を促進するため、起業に要する経費に特別交付税で財政支援を行っている(自治日報2015/9/11)。これらの事実は、市町村や国、県が明確な方針と責任を持ち、実効ある施策、条件整備を行えば、地方への移住・定住が更に広がることを如実に示している。
(3)「自治体消滅」論のねらいは何か
このように「自治体消滅」論には、それを妥当とする客観的な根拠は稀薄であり、理論的にも、実態的にも破綻していると言える。では、なぜ、増田氏らは「自治体消滅」論を先行して展開したのか。そこには急速に進む我が国の人口減少社会に対して、世論を喚起するだけではなく、政府としての総合戦略を後押しする新たな自治体再編のシナリオがあったと思われる。
政府筋では絶対に言えない「消滅可能性都市」という表現を使い、個別自治体名を名指しし、マスコミを使ってセンセーショナルな形で発信し、危機感を煽ってきた。その中で、人口減少、地方消滅と言う言葉がひとり歩きし、市町村消滅を必然と捉え、世論をそこに誘導している。端的に言えば、「全ての町は救えない、それは効率的ではない。やる気のない、頑張らない、人口減少社会の中で将来展望が描けない自治体は消滅してもやむを得ない。それは自治体の自己責任である」と言う政治的なメッセージである。
総務省の定住自立圏構想推進懇談会の残間里江子委員は、「やる気のないところは自業自得で滅びていってもしょうがない」(自治日報2014/4/4)と露骨に述べている。その意味では、政府の自治体再編戦略は、かつての市町村合併、小規模自治体の機能・役割を限定する特例団体方式(西尾私案)から一気に「自治体消滅」論、自己責任論に大きく転換している。これはまさに「ショックドクトリン」である。中山間地域フォーラムの佐藤理事長は、同会主催のシンポジウム(2014年7月)の中で、「問題を極めて単純化し、わかりやすい形で自治体の消滅可能性を提起した。住民は一度そう思い込んだら思考停止になる」「将来消滅することが明らかなら、そんな市町村には公共投資をする必要がない、税金の無駄使いであるという論理が生ずる」と述べている。
3.日本創成会議の提言
日本創成会議は、2014年5月に「ストップ少子化・地方元気戦略」を提言した。そのポイントは、①国民の「希望出生率」を実現すること、②企業の取り組みへの支援を行うこと(子育て支援、男性の働き方の見直し、残業割増率の引上げ)、③若年世代の経済基盤を強化すること(若年・結婚子育て年収500万円モデル(夫婦)、多子世帯の経済的支援、保育所の待機児童対策など)、④地方元気作戦を推進すること(東京一極集中に歯止めをかけ、若者に魅力のある新たな集積構造の構築、コンパクトな拠点+ネットワークの形成、自治体間の地域連携など)である。
これらの施策には特段目新しいものはなく、従来の施策の焼き直しであるが、それが政府の基本政策の柱になっている。それはこの間の政策形成過程をみれば明らかである。増田氏は提言発表後すぐに経済財政諮問会議の「選択する未来」委員会に加わり、9月には地方創生本部の有識者会議にも参加し、今日の「地方創生」施策づくりで中心的な役割を果たしている。
問題は、施策の中身と政府の姿勢である。例えば、若年世代の経済基盤を強化すると述べているが、この間の自民党を中心とする政権が進めてきたことは、非正規・低賃金労働者の拡大であり、今やその数は2014年11月現在2000万人を超えている。公務の場でも7万余の「公の施設」に指定管理者制度を導入し、そこで大量の官製ワーキングプアを作り出している。
増田氏らの提言や政府の施策は、女性の労働力確保が前提になっており、所得は若年・結婚子育て世代の夫婦合わせて年収500万円という低い水準である。更に安倍政権が現に進めていることは、提言の趣旨とは裏腹に“生涯ハケン”を押し付ける労働者派遣法の改悪や“残業代ゼロ”の合法化、雇用ルールの切り崩しである。まさに政府の本気度が問われている。単なるスローガンにさせず、実効ある施策の実施を国に迫っていくことが重要である。
4.「地方創生」推進に向けた政府の方針と重点施策
(1)いま、なぜ「地方創生」なのか
このことについて、平岡和久氏(立命館大学教授)は、次のように述べている。
1つは、アベノミクスの「第3の矢」である成長戦略「世界一企業が活動しやすい国づくり」に地方を動員することが必要になっていること。具体的には地方施策での規制緩和、公共部門の効率化(徹底した人件費削減と公共施設の統廃合・集約化)である。2つ目は、東京圏の活力の維持、その阻害要因となる東京圏の高齢者などの「人口」の受け皿と仕掛けづくりが求められていること。3つ目は、地方にアベノミクスが波及しておらず、今年4月の統一地方選を踏まえて地方に「光」を当てる政策が求められたこと。4つ目は、人口減少が経済成長、経済「大国化」にもたらすマイナス影響の危惧を払拭することである。詳しくは「自治と分権」2015年春号(大月書店)を参照されたい。
(2)「骨太方針2014」の人口政策論
人口減少が急速に進む中で、経済財政諮問会議は「出生率を今の『1.43』から30年に『2.07』に回復させれば、60年代でも1億人を維持できる」と述べ、出産や子育てに予算を重点化し、社会資本整備の選択と集中を行うべきと提言した。これを受けて、政府は2014年6月に「骨太方針2014」を閣議決定した。その中で「50年後に1億人程度の安定した人口構造を保持することを目指す」という目標を掲げ、「日本の未来像に向けた制度・システム改革を実施する」ことを打ち出した。
政策の柱は、①子どもへの資源配分を大胆に拡大、少子化対策を充実する、②地方自治体の創意工夫や努力がより反映されるよう、行政サービスの提供のあり方、政策手段などを大胆に見直す、③地域の活力維持、東京への一極集中傾向に歯止めをかけ、少子化と人口減少克服をめざして総合的に政策を推進する、の3点である。
経済財政諮問会議が提起した出生率「2.07」というのは、人口置換水準であり、それは日本では40数年前の高度経済成長期、第2次ベビーブーム時代の水準であり、そう簡単に実現できる目標ではない。その環境、施策をどう整備していくのか、その内実が問われる。「骨太方針2014」の目標は、50年後も1億人程度の安定した人口を維持し、生産性の向上を図って、2050年代に実質GDP成長率1.5~2%を維持することである。ここには住民の暮らし、文化、生業、地域といった視点はなく、それは労力確保、経済規模、成長率の維持を図るための手段になっている。
神野直彦氏(東京大学名誉教授)は、「人口という言葉は、人間を量として把握するために生み出された。人間が目的でなく、手段とする社会になったとき、人間は没個性の人口になる。人口をターゲットとする政策が示されたときは、人間を手段とする社会を目指し始めたと考えた方がいい」「人間を労力、兵力という手段とみるとき、どういうことになるのか、歴史を振り返ることが必要だ」(西日本新聞 2015年1月9日)と述べている。今、まさに安倍政権下で労働法制が改悪され、安保法制(いわゆる戦争法)が強行採決された。この警鐘は極めて重要である。
(3)ローカル・アベノミクスの推進が基本
「骨太方針2014」のもう1つの柱は、「成長戦略の強化・進化」であり、「ローカル・アベノミクスを通じて成長戦略の成果を全国津々浦々まで広げる」ことである。その手法は、この間の成長戦略、新自由主義的な構造改革路線を地方で推進するもので、国家戦略特区等による更なる規制緩和や民間開放の促進である。自民党の「政権公約2014」でも、「地方創生を規制改革により実現し、新たな発展モデルを構築しようとする『やる気のある、志の高い地方自治体』を、国家戦略特区における『地方創生特区』として早期に指定することにより、地域の新規産業・雇用の創出をします」との方針を明確にしている。これを踏まえて、安倍内閣は今年3月に「地方創生特区」の第一弾として、愛知県(公設民営学校の設立、農地の集約、企業の農業参入の促進等)、仙台市(地域限定保育士の導入等)、仙北市(国有林の民間利用の拡大等)を指定し、7月には国家戦略特別区域法および構造改革特別区域法を成立させた。その中には、都市公園内における保育所設置の解禁、公立学校運営の民間開放などが盛り込まれている。また、第31次地制調では、公権力の行使を含む窓口業務等の地方独立行政法人等への一括委託も検討されている。事態はここまで進んでいる。
(4)「国土のグランドデザイン2050」を公表
国土交通省も2014年7月、「本格的な人口減少社会の到来等に対する危機意識を共有し、2050年を見据えて未来を切り開いていく」として「国土のグランドデザイン2050」を公表した。
そこでは地域存続の危機(2050年の人口は約9700万人、約6割の地域で人口が半減以下になる、うち2割で人が住まなくなる)を指摘し、基本戦略として、①国土の細胞としての「小さな拠点」(全国5000カ所程度)と高次地方都市連合(全国60~70ヶ所程度)の構築、②攻めの「コンパクト+ネットワーク」の推進、③国際競争の拠点となる「グローバル経済圏」を目指し、東京、名古屋、大阪の三大都市圏をリニア新幹線で結ぶ「スーパーメガリージョン」の形成等を提起した。
「小さな拠点」とは、一定地域にある複数の集落郡を「集落生活圏」と位置付け、その中に地域再生拠点を形成し、そこに生活サービス機能(医療・介護、福祉、教育、買い物、燃料供給等)を集約し、周辺集落と地域交通ネットワーク等で結ぶという構想である。これを推進するため地域再生法を改正した。併せて優良農地の保全・活用、交通ネットワークの確保、生活サービスを提供する担い手としてNPОや株式会社など多様な地域再生推進法人を認め、交付金の直接支援対象にした。
しかし、施設の集約化で周辺部のサービスが後退しないか、利便性が確保されるのか、地域交通が長期的に維持(交付金等)されるのか、拠点地域への移住が加速されないか等の危惧、懸念がある。国交省側は、「よくある誤解」としてその払拭を図っていくとしているが、それを「誤解」と言えるのか、事実に即した検証が必要である。
「スーパーメガリージョン」の形成では、河村名古屋市長は「空前のチャンス、世界中から人の来るまちづくりを目指す」と述べ、中心部での大規模開発を構想している。また、それで三大都市圏が一体化するとしているが、実際には東京集中が更に強まるのではないか。総務省が今年2月に発表した人口移動報告をみても、東京圏への集中だけが加速して10万人超となり、大阪・名古屋圏は2年連続で転出増になっている。
(5)「新たな広域連携」の創設と財政措置
第30次地制調答申(2013年6月)は、市区町村が一律に住民の日常生活に必要不可欠な行政サービスを自己完結的にフルセットで提供し続けることは困難であり、「自主的な市町村合併や基礎自治体間の広域連携を進めること」、「今後は地方中枢拠点都市を核に都市機能、生活機能を確保するとともに集約とネットワーク化を進めていくこと」が重要であると提起した。
これを受けて総務省は、定住自立圏構想の充実・強化、集落ネットワーク圏および地方中枢拠点都市圏の創設を打ち出し、中心市(人口5万人以上)や地方中枢拠点都市(地方圏の指定都市、新中核市、昼夜間人口比率1以上で圏域を支える都市)に社会資本整備を集中し、周辺市町村と協定に基づくネットワークの形成を提起した。そのため地方自治法の一部改正を行い、自治体間の連携協約、県による事務の代替執行、新中核市制度を創設した。
その後、地方中枢拠点都市圏等の類似構想は「連携中枢都市圏」構想と改名され、今年1月に財政措置も講じられた。連携中枢都市には「経済成長の牽引」および「高次都市機能の集積・強化」の取り組みに対して圏域人口75万人規模で約2億円の普通交付税措置、「生活関連連携機能サービスの向上」の取り組みに対して1.2億円の特別交付税措置、連携市町村には1市町村当たり上限1500万円(年間)の特別交付税が措置される。
政府は、「地方創生」の核である連携中枢都市圏構想を推進するため、2014年度から「新たな広域連携モデル構築事業」を全国9団体に委託し、2015年度には更に12団体を追加した。第31次地制調でも「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制のあり方」として、広域連携にシフトした地方行政体制のあり方が検討されている。
並行して、定住自立圏の充実、強化も行った。2014年5月現在、79圏域、延べ373団体で定住自立圏形成協定又は定住自立圏形成方針を策定済みであり、93団体が中心市宣言を行っている。総務省は、第30次地制調の答申を受けて検討会を設置し、2014年度から財政措置の拡充(包括的特別交付税の引上げ)を行った。
●中心市 上限額4000万円→8500万円 ●近隣市町村 同1000万円→1500万円
今後、「地方創生」絡みで対象圏域も増え、活動も強まると想定されるが、この取り組みではすでに多くの実践例があり、その実態と課題を把握し、改善を図っていくことが必要である。
なお、広域連携は、拠点となる中枢拠点都市と周辺自治体が対等平等の関係、自治の保障の上に構築されるべきものである。今回、新たな創設された連携協約は、定住自立圏での協定とは異なり、長期的・継続的施策として展開していく観点(必要性)から、より安定的な市町村間の連携を担保する制度として地方自治法に位置付けられた。協約内容の執行に関しても、自治体間の紛争が生ずることを想定し、自治紛争処理委員会による紛争処理規定も定められた。
連携協約の内容は、目的、基本方針、連携を図る事務・取組内容・役割分担(圏域全体の経済成長の牽引、高次都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向上)、費用負担、連絡調整協議、失効等で構成されている。実質的にどんな関係で運用されていくのか、先行事例の今後の推移を見極め、検討していきたい。
辻山幸宣氏(自治総研所長)は、連携協約について「(それは)ある自治体の主権者の決定が他の自治体の住民を縛ることになる可能性がある。自治体は独立した法人格を有する。それは住民による運営・管理に根拠を持っている。地方創生という名の下に『人口減少』『消滅可能性』をちらつかせて『自治』を奪うことは許されない」(自治日報2014/10/31号)と述べている。
なお、広域連携は、実質的には合併に代わる新たな分権の受け皿づくりでもあり、連携協約がうまく機能しなければ編入合併の引き金にもなる。この点にも留意が必要である。
(6)合併算定替廃止時期とも符合
今日の自治体再編論は、分権の受け皿づくりとしての総合行政体論が基礎になっている。その手法は、基礎的自治体の規模を中核市程度に再編し、都道府県から大幅な権限を移譲し、地域完結性を有するフルセット型の自治体として再構築していくことである。そのため政府は平成の大合併を進め、その結果、1999年3月末に3232あった市町村は、2010年3月末には1727に減少した。合併で周辺部が衰退し、人口減少、過疎化に拍車をかけている。全国町村会は「合併して良かった」と言う声は殆ど聞かれないと総括している。
合併で誕生した新自治体には、10年間は交付税を上乗せする特例措置(合併算定替9304億円)が適用されているが、11年目以降は段階的に減額され、16年目以降は一本算定に移行する。その影響額は極めて大きく、合併自治体にとっては深刻な事態になる。
「合併算定替終了に伴う財政対策連絡協議会」の資料によれば、影響額が50億円以上になる自治体は14団体、30~50億円は44団体になる。また、経常一般財源に占める影響額の割合が20%以上になる自治体も9団体ある。すでに減額期に入った自治体もあり、これから本格化する。この合併算定替廃止時期が、「自治体消滅」論と重なっており、自治体によっては交付税の大幅減額が地域再生意欲の喪失や再合併の誘因になっている。そのため総務省は、2015年1月に合併自治体の要望を踏まえ、交付税の特例措置終了後の新たな財政支援措置を示した。これまでの特例措置分9304億円の約7割にあたるは6700億円(最大)を確保し、合併後の実情に応じた形で交付税の算定方法を見直し、2014年度から5年かけて段階的に新たな支援を行う。
5.政府が長期ビジョンと総合戦略を決定
(1)展望が見えず、説得力に欠ける「長期ビジョン」
政府は2014年12月に人口減対策としての「長期ビジョン」と2020年までの具体策である「総合戦略」を閣議決定した。長期ビジョンの基本認識は、①人口減少は経済社会に大きな重荷になり、地方は地域経済社会の維持が重大な局面を迎える、②的確な政策に転換すれば未来は開ける(人口減少の歯止め、希望出生率の実現、東京一極集中の是正など)、③2060年に1億人程度の人口を確保し、「人口の安定化」と「生産性の向上」が図られれば、2050年代に実質GDP成長率は1.5~2%程度が維持される、というものである。
政策の具体化では、同ビジョンは日本の厳しい状況、事実の羅列に止まっており、ビジョンとしての説得力、展望が全く見えない。今日の少子化、人口減少の原因がどこにあるのか、地方の疲弊をここまで深刻にしたのは誰なのか、その真摯な総括もない。結論的には、「出生率を向上させる方策には『これさえすれば』というような『決定打』もなければ、これまで誰も気付なかったような『奇策』もない」と述べ、地方に具体策を丸投げしている。日本の出生率の低下は以前から指摘されてきたことであり、なぜ、フランス(1993年1.66→2010年2.0)やスウェーデン(1999年1.50→2010年1.98)のように、家族給付や出産・育児と就労の両立支援など若い世代の生活の実態に寄り添った措置を講じて計画的に改善を図ってこなかったのか、その責任が問われる。
なお、ビジョンでは政府目標の「50年後に人口1億人」を実現するシナリオとして10年ごとの達成想定を示したが、「出生率1.8を目指す」等という目標設定は削除された。
(2)「総合戦略」の4つの基本目標
国の「総合戦略」の基本目標は、下記の通りである。
- ①地方に安定した雇用を創出すること(地方で若者雇用創出30万人、女性就業率73%など)
- ②地方への新しい人の流れをつくること(地方から東京圏6万人減、東京圏から地方4万人増など)
- ③若い世代の結婚・出産・子育て希望を実現すること(夫婦で計500万円の年収確保、第1子出産前後の女性継続就業率55%、結婚希望実績指標80%など)
- ④時代に合った地域づくり、地域間連携を推進すること。
数値目標については、それ自体の客観性、妥当性の検証が必要である。同時に、それは各自治体の総合戦略、数値目標と連動しており、それとの整合性が求められる。更に実現に向けては、その裏付けとなる施策の具体化、その実効性の検証も必要になる。例えば、女性の就業を前提に夫婦で500万円の年収で果たして東京で子育てができるのか、非正規、低賃金労働者が増えている中で、それ自体も実現できるのか、政府の施策が現実にそうなっているのかなど課題は多い。
(3)地域住民生活緊急支援交付金の創設と運用
政府は、今年1月に総額3.5兆円の経済対策を決定し、「地方創生」施策の目玉である地域住民生活緊急支援交付金(総額4200億円)を設けた。交付金には地域消費喚起生活支援型(2500億円)と地方創生先行型(1700億円)の2種類がある。前者は地元の商店街で使うプレミアム付き商品券とふるさと名物商品券・旅行券の発行が基本である。政府が3月に決定した交付金の配分額をみると、プレミアム付き商品券が全体の64%、ふるさと名物商品券・旅行券が25%で約9割を占める。低所得層への燃費補助、子育て支援等への助成は、残りの10%程度に過ぎない。
後者の地方創生先行型は、地方版総合戦略の策定、地域しごと支援や創業支援、小さな拠点づくりなどに助成される。この交付金には基礎交付分(1400億円)と上乗せ分(300億円)がある。上乗せ分は政策誘導を伴う競争的な交付金であり、政府の「地方創生」戦略の目玉でもあるが、それは本来の地域再生の趣旨にはなじまず、基礎交付に一本化すべきである。交付金は、人口を基本としつつ小規模団体に割増、財政力指数、就業率、人口流出、少子化状況等に配慮して交付される。これらの交付金はすべてメニュー選択型であり、その運用や使い勝手に疑問が出ている。神野直彦氏も「地域が自由に工夫できる実質が伴った交付金なら意味があるが、メニュー選択型ならミニ補助金化する恐れがある」と指摘している。
なお、政府は今年8月に2016年度に創設する「地方創生」新型交付金の「統一的方針」を決定した。来年度予算の概算要求で、内閣府は所管交付金の再編等で、各府省も裁量予算の削減等で財源を捻出し1080億円を要求した。同額の地方負担と合わせ事業費ベースで2160億円超になる。全国知事会は当初予算化を評価する一方、昨年度補正予算での先行交付金を大幅に上回る額を要求してきたことから規模への不満が出ており、地方負担分も地方財政措置を講じるよう要求している。
(4)連携中枢都市圏構想の推進
政府は、「地方創生」戦略の核である連携中枢都市圏構想を推進するため、2014年度から「新たな広域連携モデル構築事業」を全国9団体(盛岡市、姫路市、倉敷市、広島市、福山市、下関市、北九州市、熊本市、宮崎市)に委託した。圏域内市町村数は85以上になる。先行している姫路市や宮崎市等では、すでに連携中枢都市圏形成に向けて連携協約を締結し、事業を進めている。
具体の動きや取組については、「どこを目指す、地方版人口ビジョンと総合戦略」(ホームページ)を参照されたい。なお、これは「地方創生」の重点施策であり、政府は2015年度に下記の団体を追加した。今後も更に拡大していく方針である。
- ○連携中枢都市圏(新規) 12件 八戸市、山形市、郡山市、新潟市、金沢市、岐阜市、静岡市、岡山市、松山市、久留米市、長崎市、大分市 (継続) 3件 盛岡市、倉敷市、福山市
- ○都道府県(市区町村連携) 6件 千葉県、長野県、静岡県、奈良県、宮崎県、鹿児島県
- ○三大都市圏 5件 千葉市、国分寺市、茅ケ崎市、京都市、神戸市
6・持続可能な地域の活性化、再生に向けて
(1)地域内経済循環、再投資力の強化を
岡田知弘氏(京都大学教授)は、各地域での先進的な実践と成果に学び、今こそ地域内経済循環、再投資力の強化、実践的住民自治による村づくり、まちづくりを進めるべきと提起している。
①地域内にある経済主体(企業、農家、協同組合、NPO、自治体)が、毎年、地域に再投資を繰り返すことで、そこに仕事と所得が生れ、生活が維持、拡大される、②地域産業の維持・拡大を通して住民一人ひとりの生活の営みや地方自治体の税源が保障される、③地域内の再生産の維持・拡大は、生活・景観の再生産に繋がるうえ、農林水産業の営みは土地・山・海といった「自然環境」の再生産、国土の保全に寄与する。
その上で、地域経済の持続的な発展、個性あふれる地域の再構築、自治体の役割について、①地域の「宝もの」、個性の発見、②自治体による個別経営体、協同組合等への支援と再投資力の形成、③自治体施策を通した仕事・雇用の創出、④地域金融機関による地域内企業への金融円滑化、⑤大企業の地域貢献、⑥中小企業振興条例の制定、それに伴う振興計画の具体化、⑦公契約条例の制定による適正価格による公共調達などが重要になる(自治体問題研究所編「人口減少時代の地域の再生と「地方創生」の課題」参照)と提起している。これは地域経済再生施策の柱になるものである。
「フォーラムの会」など小規模自治体での先進的な取り組みでは、北海道東川町、福島県大玉村、長野県原村、阿智村、下條村等では、若者用賃貸住宅建設や住宅地の確保、定住補助金等の交付、子育て負担の軽減等で1万人以下の町村でも人口を着実に増やしている。また、U&Iターンの受け入れでは、群馬県上野村は後継者定住促進条例の制定、村営住宅の建設、雇用確保、生活補給金制度の創設等で今やIターンが人口の17%になっている。こうした取り組みは島根県海士町や岡山県西粟倉村、群馬県神流町等でも取り組まれており、それぞれに成果を上げている。
農業・林業振興では、宮崎県綾町、徳島県上勝町、秋田県羽後町、北海道訓子府町等では、自然との共生・有機農業の推進、農産加工による6次産業化、公社や集落営農組織による農業振興、農業基盤整備事業や農業の近代化、長野県根羽村では植林から建設までを一貫して行う「トータル林業の村」づくりなどが取り組まれている。
再生可能自然エネルギーの開発では、大分県九重町、徳島県上勝町、長野県原村、北海道ニセコ町等が、地熱発電や太陽光発電、木質バイオマス発電などに積極的に取り組み、北海道の下川町は豊かな森林資源を活用した森林総合産業の創造、木質バイオマス活用によるエネルギーの完全自給、誰もが安心して暮らせる高齢化に対応したまちづくりで成果を上げている。こうした実践例を全国に広げ、各自治体の地方版総合戦略の中に位置付けていくことが必要である。
(2)田園回帰の政策論、実践論
藤山浩氏は中山間地域フォーラム主催のシンポ(2014年7月)の中で、「この半世紀がもたらした限界と地元の創り直し」「人間・国土・地球環境から見て、持続可能な地域社会を再構築すること」が最重点課題であると指摘した上で、要旨次のような提言をしている。
- ①じっくり、あわてず人口の1%程度を毎年取り戻すこと。
- ②田舎は著しい外部依存体質であり、所得(域外流出額)の1%を取り戻すこと。中山間地域の特性は「小規模・分散」であり、一人勝ちの「規模の経済」は逆効果である。「合わせ技で1.0人役」を担うこと。半農半蔵人、半農半看護、半農半福祉などの働き方、稼ぎ方を実践していくこと。
- ③定住を受けとめるコミュニティづくりを進めていくこと。
- ④分散型居住を支える拠点・ネットワークを形成していくこと。
- ⑤都市と農山村の共生を実現していくこと。
これらはきめ細かな地域調査・研究に裏付けられた具体的、実践的な提言である。
(3)人口減少社会の国土計画と都市部の課題
このことについて、中山徹氏(奈良女子大学教授)は次のように述べている。
1つは、人口流出の主な理由は地方に安定した就労先がないこと。これまでは工場の地方移転、公共事業で雇用を確保してきたが、今後は第1次産業と社会保障分野で地方に雇用を確保していくこと。この分野は政策によって拡大することが可能である。2つ目は、人口減少等によって生み出されるゆとりを活用して災害に強い国土、まちをつくること。3つ目は、自然災害に対する脆弱性を克服し、自然・生活・教育環境を整え、都市の格、質を高め、大都市圏の国際化を進めること。4つ目は、市街地のコンパクト化、縮小よりも地域に人口を維持する方策を考えていくこと。集落の統合は、共同意識が失われ、より利便性の高い都市部への転出に繋がる可能性がある。5つ目は、「国土のグランドデザイン2050」では、三大都市圏のインパクトを地方拠点都市に、地方都市のインパクトを農山村に波及させ、「小さな拠点」と周辺集落をネットワークで結ぶとしているが、これはトリクルダウン理論の地域版である。地域の活性化を進めていくには、この理論を乗り越え、インパクトの波及を小規模から大規模に転換していく国土計画づくりが必要である(雑誌「経済」2014年11月号、新日本出版社)。この視点も極めて重要である。
おわりに
今日、グローバリズムの中で「経済性」と「人間性」の対立が広がり、国のあり方、施策の内実が問い直されている。住民のいのちを守り、人間らしい暮らしを築き、持続可能な地域を再生していくことは焦眉の課題である。地域の未来、自治体のあり方を決めるのは、主権者としての住民自身であり、積極的な参加、検証、提言が求められている。