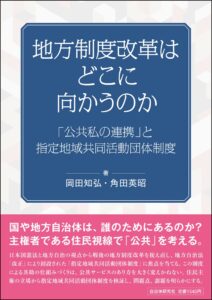団地自治会のこれまでの歩みを振り返り、成熟期を迎えるいま、取り組まなければならない課題を再検討します。
住む形の変化─団地の出現とその多様性
ひとことで「団地」(集団住宅地)といっても、その計画目標とそれにもとづく住宅地の構成や住宅戸数、設置主体はさまざまです。一般的には、団地は、独立住宅あるいは集合住宅だけで構成されるものと、両者で構成されるものとがあります。その設計理念も、近隣住区型(C・A・ペリー)のものや田園都市型(E・ハワード)のもの、あるいは規模の大小、付設される施設の種類などによって大きな開きがあります。また、その地域区画が、1つの小学校を置く規模か、それより広いか狭いか、さらには賃貸か分譲か両者の混在か、分譲住宅団地の場合では、管理組合だけか、入居者をふくむ自治会組織があるか、団地の周辺に戸建て住宅や商店がスプロール型に広がっているか相対的に独立したままなのかなど、団地といってもその姿はきわめて多様となっています。
わが国では、戦前、1891(明治24)年の濃尾地震で、レンガ造りの近代風の大きな建物が被害を受けたことで、建物の耐震化が課題とされ、1923(大正12)年の関東大震災では、火災の被害が大きかったことから、耐火構造への転換が重要な目標となっていました。
関東大震災からの復興に際しては、財団法人同潤会が設立され、市街地では、近代的な集合住宅団地(アパートメント)の建設が行われて、「快適で合理的な都市生活」の場の実現が目指されました。団地によっては、中庭、共用施設(炊事場、洗濯場、娯楽室、銭湯など)を備え、「アパート新聞」を発行するなど、共同住宅としての活動も行われていて、「団地だから人間関係が希薄」とはいえないものでした(同潤会は1941年に住宅営団に吸収されて解散し、建設された住宅も、2013年までにすべて取り壊されています)。
その後、わが国は戦争に突入し、戦災によって多くの住宅を失いました。戦後には、国外からの帰還者も含めて住宅の不足数は420万戸といわれ、さらにその後の経済の復興期になって都市部への人口の流入が大きくなると、住宅の大量供給が重要な課題とされるようになりました。さまざまな事業主体による住宅の建設がすすめられましたが、大量供給という当面の課題が先立って、同潤会が創りあげてきた近代的な集合住宅の理念を生かし、発展させることはできなかったといわれています。
こうして、戦後の「大都市圏の居住空間は、意図や目標のハッキリしないまま、無秩序に拡散してしまった」といわれるようなものとなりましたが、そのなかにあって、自治体や住宅公団などによる集合住宅団地は、限定された空間内においてではありましたが、「それぞれの時代の生活や社会が目指す最も先鋭的な像を端的に表現しえた小宇宙空間」でした。そしてそれゆえに、ニュータウンは、「新都市というよりいわば、住宅団地の集合体的な性格」のものに留まることになりました。
戦後の住宅政策と団地の普及
上述のように、戦後日本の復興にとって、住宅の確保は大きな課題でした。そのため、1950年の住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)設立による持家取得層への支援、1951年からの公営住宅の建設による低所得層を主とした借家の提供、1955年設立の日本住宅公団(現・都市再生機構)による都市中間層向けの集合住宅の整備などがすすめられました。また、民間の建設業者も集合住宅の建設を手掛けるようになり、マンションの建設も増えていきます。
高度経済成長期における都市への人口の集中は、地価の高騰による都市での住宅条件の悪化をもたらしました。そこで住宅不足の緩和のために、1960年代には、千葉県松戸市の常盤平団地(1960年入居開始、以下同じ)、大阪府下の千里ニュータウン(1962年)や泉北ニュータウン(1967年)、愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウン(1968年)などの大規模団地が建設され、1970年代以後にも、東京の多摩ニュータウン(1971年)、横浜の港北ニュータウン(1983年)と、大都市近郊地区で大規模な集合住宅団地の建設がすすめられました。それは、子育て層を中心に、都市人口の郊外へのスプロール化をもたらしましたが、バブル経済の崩壊とともに人口の都心回帰が始まり、建築基準の緩和もあって、市街地の再開発による高層住宅棟の建設がすすんできました。
住宅をめぐる国内の大きな趨勢としては、1968年には、全国レベルでは、住宅数が世帯数を上回るようになり、以後、世帯数も増え続けるのですが、空家数はそれを上回って増加してきました。国勢調査の結果では、全国人口は、2010年をピークとして2015年は95万人の減を記録しますが、世帯数はなお増加を続けています。住宅数も、世帯数の増加を上回る比率で増加していて、空家数は、2013年には、全国で820万戸に達しています(総務省「住宅・土地統計調査」)。
効率的な住宅戸数確保の観点から、当初は団地の住宅は室数も各室の面積も抑制され、入居家族モデルは核家族でした。そのために、三世代以上の同居は困難でした。また、分譲集合住宅の所有関係も、当初は「全居住者による建物の共有」という状態にとどまり、1962年に建物区分所有法が制定されて、個人所有と共同所有の区分が明確化されますが、なお「区分所有者の団体」についての規定はなく、全区分所有者が管理組合に加入することが義務付けられたのは、1983年の同法改正によってでした。
しかし、物理的には一体の構造物である分譲集合住宅で区分所有権を認めることには、国民の強い「持家意識」を満足させることが意図されていたともいわれました。また、都心地区に建設される民間高級高層マンションは、一戸ごとの面積も広く、付帯施設も充実してきて、扉を閉めてしまえば近隣との付き合いもいらず、プライバシーが守られる環境であることが売りとされました。近年は、個人情報保護のために表札を出さない世帯もあり、オートロックで外部と遮断することで住民を守ろうとするマンションが増えるなど、近隣との交流や共同より、孤立的な生活指向を強める傾向も出てきています。
他方で、自治会への住民の加入率が低下してきていることから、近年、行政の窓口で転入者に、地元自治会への加入を勧める取り組みもすすんでいます。団地でも、団地を管理するマンション管理業協会や共同住宅協会が、行政とも連携して、入居時に住民組織への加入を勧める動きも生まれています。
団地住民と共同の関係
わが国の団地は、戦後の住宅難を背景に、主に地方出身の若年層を対象に、急速に建築・整備されてきました。そのためもあって、当初の入居者は年齢や社会的階層が近い人が多く、とくに公営の賃貸住宅団地では、この特徴が顕著でした。入居が始まると、まず、保育所や小・中学校の不足、通勤・通学の交通の便の悪さなどの共通する問題に直面することになりました。そこでは、仮の住まいと思いながらも、さし当たりの生活課題の解決に取り組む動きが、各地でおきていました。1970年代の革新自治体づくりや各種の住民運動を支えた大きなエネルギー源が、こうした若い団地住民層であったことは多く見られたことでした。
高度経済成長期も末期になると住宅の不足が緩和され、団地の暮らしも、より高い水準を求める成熟期に入っていきます。住む場所探しの時代から、より豊かな住み方を模索する時代に入ってきます。「団地の40年」の始まりです。この時期は、1973年のオイルショックとその後の低成長期、バブルによる不動産価格の高騰を経て、冷戦の終了からグローバル化の時代へと続きます。その後は、新自由主義的政策の推進による社会的な格差の拡大がすすみ、貧困層のホームレス化もみられました。外国人の団地入居も増えて、日本人居住者との軋轢が起きることもありましたが、定住化がすすむと、交流が深まるようになってきました。若い世代の入居ではじまった団地も、子ども世代の転出により、今度は逆に、児童生徒数の急減による小・中学校の統廃合が問題となり、住民の高齢化と空室の増加、団地人口の減少による日常の買い物や医療、交通の便に欠ける状況が生まれてきました。これらは、過疎地でいわれる問題ですが、都市部では、郊外型の団地に現れてきています。わが国が、今後いっそうの「超高齢・少子・人口減少・単身社会」になっていくとすれば、それは、全国の地域を巻き込んでいく社会的な動きといえます。団地は、住民の居住条件と社会階層の相対的な同質性の高さのために、問題がより明確に現れるという特徴をもっています。そしてさらに建物の老朽化や被災による修理・改築などの問題の処理については、分譲団地に固有の区分所有権にかかわる問題も増えてきています。
こうして、扉を閉めれば「自律・自由な」自分の世界と考えられ、それを求めて選んだ住居であったとしても、客観的には、団地は、他の住民との密接な共有・共同利用関係にあることが明白になってきました。しかも団地は、外観的にも、その外部の地域と区別しやすい構造をもっているので、空き巣事件や孤独死の問題などが起きると、「団地の問題」と受け止められやすいという特徴もあります。こうして、団地では、生活上の問題や災害への対応など住民の協力が必要な問題が顕在化してきています。これらにたいして、住民が自治的に協力しあう体制を築くことが、ますます重要になっています。
団地自治会の組織と活動の発展
団地の暮らしは、各世帯の自立性の高さとともに、共同性の強さを特徴としています。この特徴は、マンションの取得について「管理を買え」といわれていることに端的に表れています。自治会の役割は、この管理を、住民の自治の力で(分譲住宅団地の場合には、区分所有者で組織する管理組合とともに)担うことです。いま、災害対策と住民の高齢化の問題で、ハード面でもソフト面でも、住民組織への期待は高まっています。しかし、その期待に反して、自治会の組織と活動が弱まっているという声は広く聞こえてきますが、すべての自治会がそうであるわけではありません。この特集に寄稿されている三つの自治会の活動は、現代の団地組織が到達した貴重な成果といえます。
住民が生活の場で、共同の利益(「共益」)実現のために活動することは、住民に固有の権利です。この権利の行使のために、住民は自治会などの住民組織を立ち上げて、「共益」実現のために、地域の共同管理(コ・マネジメント)を行っています。住民によるこの共同管理の目的は、規約の冒頭に掲げられるのが普通です。ただ、そこで掲げられる目的の多くはきわめて抽象的で、現実の具体的な活動の指針にはなりにくいものです。自治会活動が成果を上げるためには、まず、地域で解決すべき課題、すなわち、組織の目的が何かを具体的に明確にすることが必要です。そして普通には、すべてが一度に解決できるわけがないので、取り組むべき活動を織り込んだ計画として提示することが重要です。役員の任期が短くなりがちな現代においては、課題の明確化と計画化が、活動発展の保障として不可欠です。計画がないなかでの役員の1年交代では、前年踏襲となって活動は停滞します。それで組織の意味が薄れていくという悪循環は避けなければなりません。
役員のなり手が見つからないと心配する声も多く聞こえます。しかし、地域に貢献したいと思っている「元気な高齢者」が多いのも事実です。両者のマッチングのためには、どんな役割(仕事)が求められているかを、できるだけ具体的に提示することが重要です。それにより、「一人一役」として得意の分野で活動できること、および過大な負担でないことを明示することができます。
人材を得るための条件の一つに、住民組織の規模の問題があります。地縁関係の範囲は狭域から広域まで重層的に広がり、それらが、基本となる組織単位を軸に、その下部の近隣組織と上部の連合組織とにつながっています。町内会・自治会のカバーする世帯数は、2006年の調査では、全国平均で200世帯未満が70%で、500世帯以上は12%に過ぎません。現代のように、地域活動においても専門分化が進むと、多様な得意技をもつ住民を集められることが有利な条件となります。そのためには、組織の範囲が、小学校区という歴史的な背景となかば公的性格をもつ広さの区域であることは、重要な意味をもちます。この時の小学校区の自治組織は、単一の自治会であることも、連合自治会であることもあり、さらには自治会以外の地域諸組織が連携した「住みよいまちをつくる会」や地域自治協議会のようなかたちもあります。いずれにせよ、団地は比較的に広域的であり、それが自治的活動の発展にとって有利な条件となっています。それが十分に生かされていないケースも少なくありませんが、人材は、いないのでなく、発掘しきれていないのです。他方で、基本となる組織が広域であるときには、その足元の狭域の近隣組織にどういう役割を果たしてもらうかも、重要な課題です。近隣組織の強みは、日常的、継続的に接点があるということです。とくに親しいということでなくても、「いつもと違う」という気づきは日常的な近さに固有のものです。何か通常とは違う状態、たとえば物音や人の出入り、郵便受けに新聞などがたまったままなどは、近所というつながりがあるから気づくことです。名古屋市緑区の市営森の里団地自治会は、不測の事態に備えて、希望者から自宅ドアの鍵を預かる制度をつくっていますが、それが可能なのも、こうしたつながりを生かしているからです。長野県茅野市の福祉計画が、第一次(2000年)で生活圏を五層にわけて最底層を「区・自治会」としていたのを、第二次計画(2010年)では七層に分け、第六層を「町会・班」、第七層を「隣組」としたのも、この近隣社会の意味を重視するからです。
地域連携による地域資源の活用
団地自治会のこれまでの歩みを振り返り、いま取り組まなければならない課題を検討することが、この特集の目的です。その際、団地という比較的大きな地域資源を抱える組織が主題であるだけに、課題の規模も大きくなります。交通手段を欠く住民の買物や病院通いなどのために団地バスを走らせるのも、ボランティアを生かしながらではありますが、それが事業として継続して成り立つ規模であることも無視できないでしょう。
こうして、団地に必要な活動の内容が明らかになってくると、その担い手は住民に限らなくてもよいことも見えてきます。
これまでの自治会活動は、「世帯内の問題は世帯で解決する」ことを基本として、もっぱら世帯外の問題(地域の美化や交通安全の活動)に重点を置く傾向がありました。世帯規模の縮小と住民の高齢化で、「世帯内で解決できない」問題が増えてくることで、個人の問題を取り上げなければならない状況が生まれています。とはいえ、「世帯内の問題は世帯で解決」すべし、という伝統的な価値意識から、隣人が世帯に立ち入ることを忌避しがちなことも確かです。世帯のなかの元気な一人が自治会の活動に参加していればすんだ時代から、外に出られない住民が増えてくると、自治会活動の先細りが見えてきます。自治会活動が、外へ出難い住民の事情を理解し、そういう住民を支える活動にも取り組むことが期待され、また避けられなくなっています。
世帯では解決できない問題のもう一つは、地震などの大災害が起きたときの対応です。同じ団地内でも、建物や階ごとに事情が違うことも起こります。今までにない専門的な判断や技術力が必要になります。さらには、冬のインフルエンザの流行や夏場の熱中症への対策、子育てや高齢者介護の場での戸惑いや虐待の問題など、団地住民の力だけでは解決困難な問題も多く発生してきています。
こうした多様で深刻な問題に立ち向かい、住民の生活を守っていくためには、社会福祉協議会や地域包括支援センター、保健所の支援や協力を得るのはもちろんのこと、共通するテーマに取り組んでいるNPOなどの市民団体や、地域内外で営業している企業団体との連携・協働も見えてきます。本誌の2016年1月号の自治会特集で紹介された名古屋市天白区平針団地自治会の月刊の機関紙には、毎号「保健所だより」というコーナーがあって、健康維持に必要な時期ごとの情報を提供してもらっています。社会福祉協議会と協力して「いきいきサロン」を開いている自治会は多いでしょう。防災に取り組むNPOとの連携による実践的な防災学習や訓練、その場に地元の建築業者が機材を持ち込んで、災害救助や道路・家屋の復旧作業などのデモンストレーションをするといった、より実際的な活動を行っている学区組織もあります。
こうして、広く人材を集め、協働体制を築いていくことは、活動の発展と、組織に対する信頼を高めることに貢献するでしょう。そしてそのためには、オープンな情報開示が不可欠です。定期的な広報の発行と各戸配布(全世帯参加の運動にしていくためには、大変であっても、非加入世帯を含む全世帯への配布)や、今後はネット上でのホームページの開設も重要となっています。こうした、地域の「全体計画と広報」を基礎に置く活動は、住民の参加の接点を広げ、安心できる日常的な管理体制の整備につながっていきます。
住民間の個別の問題(たとえば、共益費の滞納、騒音、障害物放置など)についての隣人間の苦情の処理も、解決すべき重要な課題ですが、住民相互の関係が深まれば、「隣人の生活音に安心感」を覚えるような関係も生まれてきます。
さらに、団地の成熟とともに、団地外の組織との交流の拡大や、団地周縁部での減築、地域の自然環境の修復を含めた地域イメージの再創造の活動にも目を向けることができるようになっていくのではないでしょうか。
【注】
- 1 名古屋市『新修名古屋市史』第5巻、2000年、第八章第一節、参照
- 2 石田頼房『日本近現代都市計画の展開1868-2003』自治体研究社、2004年、他
- 3 佐藤滋『集合住宅団地の変遷』鹿島出版会、1989、7頁
- 4 同、11頁
- 5 稲本洋之助他『コメンタール・マンション区分所有法』日本評論社、1997年、.なお、竹井隆人『集合住宅と日本人』平凡社、2007年、49─50頁も参照
- 6 若林靖永・樋口恵子編『2050年 超高齢社会のコミュニティ構想』岩波書店、2015年、「はじめに」
- 7 谷口浩司編著『マンション管理評価読本』学芸出版社、2012年
- 8 辻中豊他『現代日本の自治会・町内会』木鐸社、2009年、50頁
- 9 『中日新聞』「発言」欄、2016年11月20日
- 10 服部圭郎『ドイツ・縮小時代の都市デザイン』学芸出版社、2016年