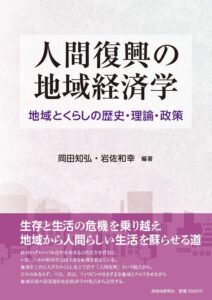オスプレイ墜落後の一連の経過が示すこの国の「対米属国」「先米軍」「沖縄差別」ぶりは、2017年度予算案にも色濃く反映されている。地方自治体への歳出抑制を継続し、地方交付税財源の確保を怠る一方で、自治体を「成果主義」に動員する方向が明確になりつつある。
日本はすでに軍事国家ではないか
2016年12月13日夜、沖縄県名護市安部の沿岸部にオスプレイが墜落しました。沖縄県副知事の抗議に対し米四軍調整官は、謝罪するどころか「住宅や県民に被害を与えなかったことは感謝されるべきだ」と発言したとのことです。事故の現場には日本側が立ち入ることができず、海上保安庁が航空危険行為処罰法違反容疑での立件を目指して捜査に着手し米軍側に捜査協力を申し入れたものの、回答がなく事実上拒否されました。事故原因も明らかでないのに米軍は同月19日には飛行を再開し、それを日本政府も容認しました。事故発生当時国会は開会中でしたが、管見の限りでは、この事故を問題にした形跡はないと思われます。
いずれにせよ、オスプレイ墜落と飛行再開に至るまでの日本政府の対応は、この国の政治の度しがたい「対米属国」「先米軍」「沖縄差別」ぶりを改めて如実に示したのではないでしょうか。オスプレイは今後、沖縄以外の米軍基地にも配備されます。日本政府も17機購入を予定しており、2017年度予算案に4機分を計上しています。今後は日本全国どこでもオスプレイ墜落に怯えながらの生活となります。
後に見るように、日本の国家予算にしめる防衛関係費は5%余りです。これは戦前と比べると格段に少なく、これだけみると軍事国家とは言えないかもしれません。しかし、本研究所の元理事長である故島恭彦先生が、政府機能を測る尺度として経費に加えて注目すべきと強調した政府雇用と政府資産をみるとどうでしょうか。
表1は、国家公務員の予算定員について、2000年度から最近までの推移をみたものです。2000年度の定員は114万5985人でしたが、5年後の2005年度には62万6732人と大きく減少しています。これは主として特別会計における総務省所管分約29万人と文部科学省所管分約13万人の消滅によるものです。前者は郵政民営化、後者は国立大学の独立行政法人化の結果でしょう。その後も予算定員は少しずつ減り続け、2016年度末では58万5632人ですが、うち自衛官が24万7154人、これに自衛官ではない防衛省職員2万1067人を加えますと、半分近くを防衛省の公務員でしめていることになります。なお、国家公務員でありませんが、2016年度から2020年度までの日米地位協定特別協定によって日本側が負担する基地従業員の労務費の上限数が、2015年度までの特別協定の2万2625人から2万3178人へと増加していることも付け加えておくこととします。

政府資産、つまり国有財産はどうでしょう。国有財産法第2条に規定されている国有財産は、土地、建物、船舶、航空機、地上権、特許権、政府出資などで、それらは国の行政の用に供するために所有する行政財産と、それ以外の普通財産とに分類されます。このうち土地の状況をみてみましょう。2015年3月31日現在の国有財産の土地は面積で8万7651平方㌔㍍あり、これは国土面積の約23%をしめます。表2は、その大半をしめる行政財産(土地)の現況をみたものです。面積では森林経営用財産がほとんどをしめていますが、庁舎や公務員住宅に使われる公用財産についてみると、面積では8割以上が、価格においても4割近くが防衛省所管であることがわかります。かつては文部科学省が旧防衛庁に匹敵するほどの比重をしめていたのですが、その多くの資産が独立行政法人化によって国立大学法人に出資されてしまいました。さらに表3は、普通財産(土地)についてみたものです。面積では山林原野が83%をしめますが、残り17%のうち在日米軍への提供地が6・9%です。その価格では全体の4割以上をしめているのは、首都圏の横田基地、厚木基地など経済的価値が相対的に高いところが提供されていることによると思われます。しかも、日米地位協定にもとづく特例措置として無償で提供されています。


以上をもって日本が軍事国家であると断定するのは早計かもしれませんが、国においては防衛に関する公務員や財産が大きな比重を占めていることは確かです。ちなみに、島先生は、1956年度末に防衛庁財産が国立学校財産を上回るようになったことに注目して、「軍事財産が一国の文化教育を支える財産を上回るようになったということは、非常に象徴的である」と述べています。
2017年度予算案の注目点
それでは、2017年度予算案をみることとしましょう。表4は主な歳出と歳入の内訳を示したものです。一般会計の歳出総額は前年度当初比0・8%増の97兆4547億円で、当初予算としては5年連続で過去最大を更新しています。伸び率をみますと、とくに目立った伸び率を示したものはなく、税収が増えないなかで社会保障関係費が多くをしめたため、あまり特色がないようにみえます。しかし、子細にみると現政権の特色が現れています。まず歳入ですが、歳出が増えて税収が前年度当初比とほとんど変わらないにもかかわらず、国債発行額がわずかに減じています。それは「その他収入」が14・7%も増えていることによります。これは、外国為替資金特別会計の剰余金2兆5188億円について、通常は7割ほどしか一般会計で使えないのに、すべて使えることにしたためです。ちなみに、国債以外の歳入で政策経費をどれだけ賄えるかを示す指標である基礎的財政収支は、小幅ながら5年ぶりに悪化し10兆8413億円の赤字となっています。

もはや4年も続けた「アベノミクス」と称する政策の行き詰まりはだれの目にも明らかですが、そもそも補正予算をたびたび組んで景気対策を講じていること自体が失敗を証明しているといえます。たとえば2016年度の補正は3次にわたっており、当初予算から歳出は3兆5000億円ほど、新規国債発行も4兆5000億円ほど増えています。筆者は、1998年・2009年に続いて3度目の本誌の予算案の執筆ですが、当初予算では財政再建に取り組んでいるように見せながら、補正予算で効果に乏しい景気対策を行ない財政赤字を膨らませるという指摘を三たびせざるを得ないことに唖然とするばかりです。これでは「ワニの口」といわれる歳出と税収の差が改善しないのは、当然といえましょう。
現首相は、前政権より消費税率5%引き上げというプレゼント付きで政権を譲り受けました。しかも、衆議院のみならず参議院でも与党が過半の議席を獲得しました。これだけ有利な条件を獲得しているにもかかわらず、経済をよくすることも、財政収支を改善することもできていないのです。加えて、消費税率の8%から10%への引き上げを延期する際には、「再び延期することはない。ここでみなさんに、はっきりと断言する」と約束したにもかかわらず、2016年6月の先送り会見では「新しい判断」と取り繕いました。消費税の増税が適切かどうかはともかく、多くの人々は、公共サービスの充実のために負担増を受け入れる覚悟はあると思います。しかし現政権には、新たな財源を活用して人々の政府に対する信頼を獲得するような施策を講じる能力がないといわざるを得ません。
歳出はどうでしょう。まず、社会保障費や地方交付税などの縮小には躍起になる一方で、防衛費は概算要求5兆1685億円と比べ400億円ほど減の5兆1251億円と(契約ベース)、要求がほぼ認められたことを強調しておきます。オスプレイも4機391億円の調達費が計上されています。防衛費は現政権になって5年連続で増加し、2年連続で5兆円を超えています。実は、これ以外にも「特別委員会関係経費」「米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分」という防衛省所管経費があります。これらの主たる内容は、辺野古新基地建設経費など米軍に提供する新基地建設のための経費です。2017年度には約2400億円計上され、うち辺野古新基地建設関連が約1700億円です。これらが毎年の防衛予算とは別枠で計上されているのです。
先に当初予算は抑制気味でも補正予算で膨らませる手法を批判しましたが、現政権の軍事優先ぶりは、この補正予算に防衛費を計上していることにも現れています。現政権発足後まもなく2012年度補正予算が組まれましたが、防衛省に2124億円計上されました。そのほとんどが「緊急経済対策」によるものでした。以後、2013年度1197億円、2014年度2110億円、2015年度1966億円、そして2016年度は2次補正と3次補正で合わせて1923億円が計上されています。2016年度3次補正は、税収の減少により特例公債を1兆7512億円も追加発行して編成されたのですが、そこに防衛費が1700億円も計上されたのです。ちなみに、防衛省のホームページにアクセスすると2000年度からの予算を見ることができます。それによると、2012年度以前に補正予算が組まれたのは2001年度だけです。
防衛予算を子細にみると、次の2つの経費の突出した伸びが目につきます。1つは大学などの研究機関を対象にした研究助成である「安全保障技術研究推進制度」です。制度開始の2015年度が3億円、2016年度は6億円だったのが、2017年度は何と110億円に増えています。従来は研究期間1年で年間最大約3000万円が支給されていましたが、2017年度からは1件あたり5年で数億から数十億円の大規模プロジェクトが新設されます。国立大学の運営費交付金など大学運営の基礎的経費の縮小が続く一方で、こうした予算が大幅に増えているのは誠に憂慮すべき事態というほかありません。
もう1つは「再編関連特別地域支援事業補助金」です。これは、名護市の辺野古、豊原、久志の3行政区だけを対象とした補助金です。政府が建設を強行しようとしている新基地の所在地がこの3区です。行政区とはいってもあくまで任意団体です。周知のごとく、2010年1月の名護市長選挙で新基地建設反対を公約に掲げた稲嶺進氏が当選して以来、各種選挙で示された新基地反対が多数をしめる名護市民をはじめとする沖縄県民の民意は明確です。政府は、こうした沖縄の民意を一顧だにしないで基地建設を強行する一方で、2015年11月に3区だけを対象として名護市の頭越しに交付するこの補助金を新設しました。15年度は1区当たり1300万円、計3900万円でしたが、2016年度は1区当たり2600万円、計7800万円に倍増し、そして2017年度は1区当たり3500万円、計1億500万円に増やしています。こうした自治権の侵害というべき予算の増額ぶりにも現政権の特異性がよく現れています。
「成果主義」に動員される自治体
総務省に設置されている地方財政審議会は、総務省設置法第9条第3項に基づく意見を毎年発表しています。ここ数年のそれを読むと、地方財政の歳出の状況について同様の指摘が繰り返されています。以下は、最新の2016年12月「意見」からの引用です。
「地方財政計画における近年の歳出は、歳出特別枠を含めてもほぼ横ばいで推移してきた。しかしながら、その内容を見ると、国の制度に基づく社会保障関係経費が増加しており、その増加分を、給与関係経費や投資的経費(単独)の減で吸収してきた。このため、給与関係経費、投資的経費ともに、ピーク時から大幅に減少しており、喫緊の課題への取組も求められる中、これまでと同様の対応を続けることは困難となってきている」
図1は、その説明資料として添付されている地方財政計画の歳出の推移をみたものです。それによると、2001年度の89・3兆円をピークに減少を続け、2012・2013年度は81・9兆円と、2001年度比で7・4兆円もの減少となっています。この間の投資的経費(単独)は、18兆円から5兆円へ、給与関係経費は24兆円から20兆円へと減少しています。

給与関係経費の減少を反映して、地方公務員の数は、1994年度の328万人をピークに22年連続して減少し、2016年度は273万人にまで落ち込んでいます。その内訳をみると、警察・消防部門は10%ほど増であるのに対し、一般行政・教育部門が20%以上減少しています。その一方で、地方自治体で働く非正規職員が増えています。総務省の調査によると、2016年4月現在の臨時・非常勤職員の総数は64万4725人で、前回の2012年調査から4万5748人増加しています。職種別では事務補助職員が約10万人と最も多く、次いで教員・講師が約9万人、保育所保育士が約6万人、給食調理師が約4万人、図書館職員・看護師がそれぞれ約1万6000人となっています。要するに仕事はあるにもかかわらず正規職員が減らされたために、非正規職員で補わざるを得ない状況が進行していることがうかがえます。
これに関して地方財政審議会は、2014年6月「意見」では「これまでと同じように地方公務員の数を削減することは困難」と述べていましたが、2015年12月および2016年12月「意見」では「限界にきている」とまで述べています。
これだけ歳出の抑制に努めても、この間の地方財政の借入金残高は200兆円とほぼ横ばいです。しかしその内訳をみると、投資的経費の減少を反映して建設地方債の残高は減少する一方で、財源不足に対応するための臨時財政対策債が大きく増加し、2016年度残高は52兆円となっています。
臨時財政対策債の発行は2001年度からですが、それは次のような経緯によります。1970代後半から恒常的に発生している財源不足の補填については、一部は財源対策債という建設地方債で補填した上で、残りは交付税特別会計借入金によりまかない、その償還を国と地方が折半して負担する措置を講じてきました。しかし2001年度からは、国負担分については国の一般会計からの加算により、地方負担分については臨時財政対策債により補填することとしました。しかしながら、毎年多額の財源不足が生じているのですから、本来なら地方交付税法第6条の3第2項の規定(毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き地方団体の財源不足額の合算額と著しく不足する場合)に該当するとみなして法定率の引き上げで対処すべきです。にもかかわらず、国と地方とが折半して補填するルールによって発行を余儀なくされたのが臨時財政対策債なのです。いずれにせよ、地方自治体が歳出抑制に努めているにもかかわらず、国が本来おこなうべき法定率の引き上げをおこなわないために地方の債務残高が減らないのは理不尽というしかありません。
高齢者の増加、少子化などにともない地方自治体に求められる役割は高まるばかりです。地方歳出の縮小・抑制政策に歯止めをかけるとともに、自治体が安定して公共サービスを提供できるようにするべく地方交付税総額の安定した確保が必要です。したがって財源不足額の補填については、臨時財政対策債のような応急措置はできるだけ早く解消することが求められています。というのは、地方財政審議会「意見」でも強調されているように、国の予算案決定後まもなく発表される地方財政計画は、自治体が標準的な行政サービスを行うための経費を計上したものであり、その財源を確保することは国の責務であるからです。2017年度予算案はそれに応える内容になっているでしょうか。
表5は、2016年12月22日に発表された2017年度地方財政対策の概要で示された来年度地方財政の姿です。それによると、地方財政計画の規模は16年度比8500億円(1・0%)増の86兆6100億円、一般歳出は7100億円(1・0%)増の70兆6300億円、一般財源総額は4011億円(0・7%)増の62兆803億円、そして地方交付税の総額は3705億円(2・2%)減の16兆3298億円となっています。

問題は財源不足額が6兆9710億円と、2016年度5兆6063億円より1兆3647億円(24・3%)も増えていること、この不足分のおよそ3分の2が先に述べた臨時財政対策債4兆452億円の発行で賄うとされていることです。地方債の総額は3300億円(3・7%)増の9兆1907億円ですが、うち、通常債は4兆3555億円と半分以下で、半分以上は本来なら地方交付税で手当てされるべき財源対策債と臨時財政対策債なのです。これでは、安定した財政基盤の確立にほど遠いというべきでしょう。
さて福祉や教育など基礎的なサービスの予算確保とともに、多くの自治体が直面している課題が、地域経済の衰退をどう食い止めるかでしょう。政府もそれを支援しようということでしょうか、三位一体改革が終了した2006年の翌2007年に「頑張る地方応援プログラム」が始まり、最近の「地方創生」に至るまで毎年のように地方経済の立て直しを支援する施策が地方交付税の算定に盛り込まれています(表6)。

「頑張る地方応援プログラム」とは、「やる気のある地方が自由に独自の施策を展開することにより、『魅力ある地方』に生まれ変わるよう、地方独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地方自治体に対し、地方交付税等の支援措置を講じる」ものであり、2007年度は2700億円程度が交付税措置されました。2017年度予算案でも、「まち・ひと・しごと創生事業費」が1兆円、地域経済基盤強化・雇用等対策費が1950億円盛り込まれています。これら一連の施策におおむむね見られる共通点は、具体的な成果を算定の指標にしていることです。頑張る地方応援プログラムの場合、「頑張りの成果」として農業産出額、製造品出荷額など9指標がかかげられていました。2015年度にはじまった「まち・ひと・しごと創生事業費」のうち、地域の元気創造事業費の地域経済活性化分や人口減少等特別対策事業費の取り組みの成果分も同様の成果指標にもとづいて措置されます。
そもそも、全国すべての自治体を対象にナショナルミニマムといわれる基礎的・必需的サービスを担えるように配分するための地方交付税を、このような施策に使うことが適切でしょうか。先に述べたように、交付税財源の不足を補填するために、地方交付税法の趣旨に反して毎年多額の臨時財政対策債が発行されています。これら成果主義的な措置に充当される財源は、臨時財政対策債の減額に充てられるべきではないでしょうか。
また、地域の元気創造事業費は4000億円のうち職員数の削減率や人件費削減率など「行革努力分」が3000億円となっています。そしてこれを後押しするように、2016年度から交付税の算定において、「トップランナー方式」が導入されました。これは、多くの自治体が民間委託、指定管理者制度導入などの経費の削減に取り組んでいる業務について、それを反映した経費水準を単位費用の積算に反映させようとするものです。さしあたり学校用務員事務、ごみ収集、庶務業務など16業務について3~5年程度をかけて段階的に反映させようとしています。
いまのところ対象となっているのが、膨大な自治体の業務のごく一部にとどまっているのは、人々の暮らしを支える基本的サービスを提供する地方自治体の仕事に、こうした「成果主義」はなじまないからと思われます。しかし、厳しい歳出抑制を余儀なくされているなかで、少しでも多くの予算を獲得するべく、手っ取り早い「成果」が得られる方向に自治体が動員されるのではないか、危惧されるところです。
先に紹介した地方財政審議会の「意見」は、増加する社会保障関係費の増加分を給与関係費などの減で吸収する「これまでと同様の対応を続けることは困難」、地方公務員の削減も「限界」と指摘しています。しかし来年度予算もこうした「困難」と「限界」を地方自治体に迫る方向は変わらないというほかありません。
【注】
- 1 島恭彦(1960)『現代の国家と財政の理論』三一書房(島恭彦(1983)『国家独占資本主義論(著作集第5巻)』有斐閣に再録)
- 2 ただし、5月に編成された1次補正は熊本地震への対応によるものです。その規模は7780億円ですが、すべて既定経費の減額で賄われています。
- 3 契約ベースとは、当該年度に結ぶ契約額の合計、つまり2017年度の契約に基づき、2017年度に支払われる経費と、2018年度以降に支払われる経費(新規後年度負担額)の合計を意味します。これは、装備品の取得や施設整備などの事業が複数年度にわたるためです。ちなみに、当該年度に支払われる額は歳出ベースといい、2017年度予算額は4兆8996億円です。
- 4 この補助金の詳細については、川瀬光義(2016)「日本政府は地方自治を放棄した」TBS『調査情報』第531号、を参照してください。
- 5 地方財政審議会『今後目指すべき地方財政の姿と平成29年度の地方財政への対応についての意見』2016年12月14日。
- 6 詳細は、総務省『2016年地方公共団体定員管理調査結果の概要』を参照してください。
- 7 総務省『地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査』2016年9月13日発表。