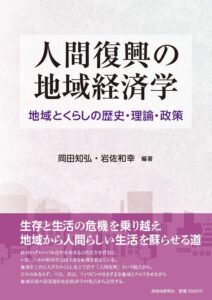種子法の廃止は、国民の食料と健康に国は責任を持たないといわれたようなものです。地方自治の力を発揮して種子法に代わる条例を定め、豊かな農と食、健康と安心できる未来を守る取り組みを紹介します。
種子条例制定に向けた長野県の動き
長野県が2019年2月に出した「長野県主要農作物等種子条例(仮称)」の骨子案は、対象作物を「稲、麦類、大豆に本県特産のそばを加えた主要農作物、本県の多様な食文化を支える『信州の伝統野菜』及び将来に向けて種子生産を継続する必要がある在来品種とする」という内容で、国が廃止した主要農作物種子法(以下、種子法)の枠を超え対象作物を広げているのが特徴です。
県民が種子法に関心を寄せはじめたのは2018年初頭。県内で種子や食に関する学習会が開かれ、講師に「日本の種子(たね)を守る会」から印鑰智哉氏や山田正彦元農水大臣らが招かれました。そこで世界の動きと先例を学び、種子法の廃止が食料を選ぶ権利や健康にも影響することを知ったのです。
「子どもの食・農を守る会伊那谷」は、伊那市や駒ケ根市などの議会で意見書を採択させ、県議会への「主要農作物の種子の安定供給・品質確保に関する意見書」提出へとつながりました。「NAGANO農と食の会」が働きかけた長野市議会も請願を採択しました。その後、任期満了に伴う県知事選挙に向け3選を目指す阿部守一知事が、基本政策集に「県種子条例の制定」を盛り込むに至りました。
このごろ、それまで別々に活動していた団体やグループがインターネットなどで互いの動きを知り、情報を交換するようになってきました。「NAGANO農と食の会」は2018年10月、農業者と消費者が守りたいものを「長野県種子多様性基本条例私案」にまとめ、これを参考に県へ思いを伝えようと呼びかけ、県内各地で講演会や学習会が次々と開かれていきました。

種子法廃止の裏側にいる「民間」
2018年4月、国の種子法が廃止されました。同法は戦中から戦後にかけ食料難を経験した日本が1952年に「二度と国民を飢えさせない」、「食料を確保するためには種子が大事」という意思を表した国民の食料安全保障の根幹をなす法律でした。種子法の廃止は、「国民の食料にもう国は責任を持たない」といわれたに等しいと思えます。
その端緒は、2016年10月の規制改革推進会議農業ワーキング・グループと未来投資会議の合同会合でした。「種子・種苗は、民間活力を最大限に生かした開発・供給体制を構築」、「民間の品種開発意欲を阻害している種子法は廃止する」と提起されていたのです。規制改革会議の名は、TPP(環太平洋経済連携協定)の署名式が行われた2016年2月4日に日米間で交わされた交換文書に登場しています。「日本政府は米国の投資家の要望を聴取して(中略)、規制改革会議の提言に従って必要な措置をとる」という内容でした。
さらに、2017年8月に施行された「農業競争力強化支援法」の第8条の4では、「(前略)都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進すること」と定められました。
自家採種も禁じて種子を「買うモノ」に
種子法廃止法案を可決する際、参議院農林水産委員会が付帯決議を採択しています。その一つに「種子の品質確保のため、種苗法に基づき、適切な基準を定め、運用する」とありますが、もともと種苗法は品種を登録した育成者の権利(知的財産権)を守る法律で、種子法とは趣旨が異なります。なにが「適切な基準」で、どのように「運用」するのかは、明らかにされていません。
種苗法では、第21条で「育成者権の効力が及ばない範囲」を定め、農業者の自家増殖(収穫物の一部を次期作付用の種苗として使用すること)を認める一方で、農林水産省令で「例外的に育成者権の効力が及ぶもの」を定めています。この例外は、1998年に23品種だけでしたが、2018年には357品種と激増しているのです。農業資材審議会種苗分科会の議事録によると、「自家増殖禁止は、今後すべての植物を対象にしていく方針」としています(2018年5月15日付けの日本農業新聞が一面トップで「種苗の自家採種『原則禁止』へ転換」と報じています)。
種子法に基づいて都道府県が供給してきた公的な種子がなくなり、農業者自身の自家採種も禁じられれば、種子はおのずと「民間事業者から買うモノ」にならざるを得ません。
種子を支配する最大手企業と発がん性のある農薬
世界で民間事業者が提供する種子は「遺伝子組み換え種子」が主で、アメリカに本社があったバイオ化学メーカーのモンサント社(2018年にドイツのバイエル社が買収)が多くを占めています。モンサント社はベトナム戦争で使われた枯葉剤と除草剤「ラウンドアップ」(有効成分:グリホサート)を開発したメーカーです。遺伝子工学で1代しか発芽しない種子(F1種子)を作り、さらにラウンドアップの廃液のなかで生きていた微生物の遺伝子を組み込んで、ラウンドアップを使っても枯れない遺伝子組み換えのダイズ、トウモロコシ、ナタネ、ワタ、テンサイ、アルファルファなどをつくり、種子とラウンドアップとのセット販売でもうけを大きくしたのです。
そのラウンドアップに世界を揺るがす判決が下されました。2018年8月10日、カリフォルニア州の陪審は、ラウンドアップが原因で悪性リンパ腫を発症したと訴えた裁判で、モンサント社に対し2億8900万ドル(日本円で約320億円)の損害賠償金を命じたのです。2019年5月の3例目となった判決では、モンサントを買収したバイエルに対して日本円で約2200億円の支払いを命じています。(2019年5月14日のNHK NEWS WEBで報じられ、「全米で同様の訴訟が1万3000件以上起こされています」とあります)
現在、世界各国でラウンドアップの使用禁止が広がっています。オランダはすでに使用禁止。フランスとイタリア、ドイツでは3年以内にグリホサートの使用を禁止することなどが決まっています。
一方、日本は2017年12月25日、グリホサートの残留基準値を最大400倍に緩和しました。世界保健機関(WHO)が2015年に「人に対して発がん性をもつ可能性」があると発表していたにも関わらず、日本は世界の逆を行っているのです。
食べものも選べず、広がる健康不安
種子が民間事業者に支配されたら消費者は食べるものを選べず、「民間事業者から与えられたモノ」でしか生きられなくなってしまいます。健康への影響も心配です。アメリカでは現在、アレルギーや発達障害、内臓疾患、肥満、糖尿病、自閉症、うつ病などに苦しむ子どもたちのためを考えた母親たちの取り組みが大きな社会現象になり、Non-GMO(非遺伝子組み換え作物)と有機農産物の消費が増え続けています。
2018年12月14日、衆議院第一議員会館で「日本の食を変えたい実行委員会」が主催する学習会が開かれ、GMO反対運動を進めているマムズ・アクロス・アメリカの創設者であるゼン・ハニーガットさんが講演しました。「家庭内でGMOを取らない生活をはじめたところ、激しいアレルギーで苦しんでいた子どもが4カ月で改善した。そこで、この経験を他のお母さんたちと共有することを始めた。百人、千人と母親たちが集まって、子どもたちの健康状態が改善していった」という事実が、病に苦しむ子どもたちと家族を助けています。一消費者がさまざまな病気とGMOとの因果関係を科学的に証明することはできなくても、食べるものを変えることならできるのです。
日本もアメリカ同様、アレルギーや発達障害、自閉症などに苦しむ子どもたちが増えています。しかもテレビでは、「日本人の2人に1人が、がんになる時代」と、当たり前のように宣伝しているのです。「遺伝子組換え技術は、暮らしに役立つ可能性を育てています」と謳う「バイテク情報普及会」のホームページ(https://cbijapan.com/、アクセス日2019年5月20日)によると、「日本人が1年間に消費するGMOの量は、コメの年間消費量(約770万㌧)の2倍以上に相当」するそうです。いつの間にか大量のGMOを消費している日本人こそ、食べるものを選ばなければなりません。
家族農業と地方の条例で守りたいもの
世界では、農業のあり方も大きく方向を変えています。これまでの大規模で工業的な農業から、自然と生態系の力を生かすアグロエコロジーと小規模家族農業へと動き出しています。国連総会で2018年12月17日、「小農および農村で働く人びとの権利宣言」が採択され、今年から国連の「家族農業の10年」がはじまっています。
人の手が届く範囲の規模であれば、民間企業の種子や発がん性のある農薬を使う必要はありません。古くから栽培されてきた在来種を守ることは、地域の食文化を守ることにもつながります。なによりも食べものは、買うモノではなく「自然からの恵み」であったことを思い返し、手軽さや便利さよりも自分で信じられる安心なものを選ぶべきです。
種子法を廃止した日本政府は、国民の食料と健康に責任を持たず、企業のビジネスしか考えていないようです。世界の逆を行く国をあてにせず地方自治の力を発揮して、多様な種子と農業者の自由な栽培、消費者が食を選べる機会、だれもが健康で安心して暮らせる社会、子どもたちの未来を守るための条例を定めたい。長野県の種子条例が、その一端になれればと願っています。