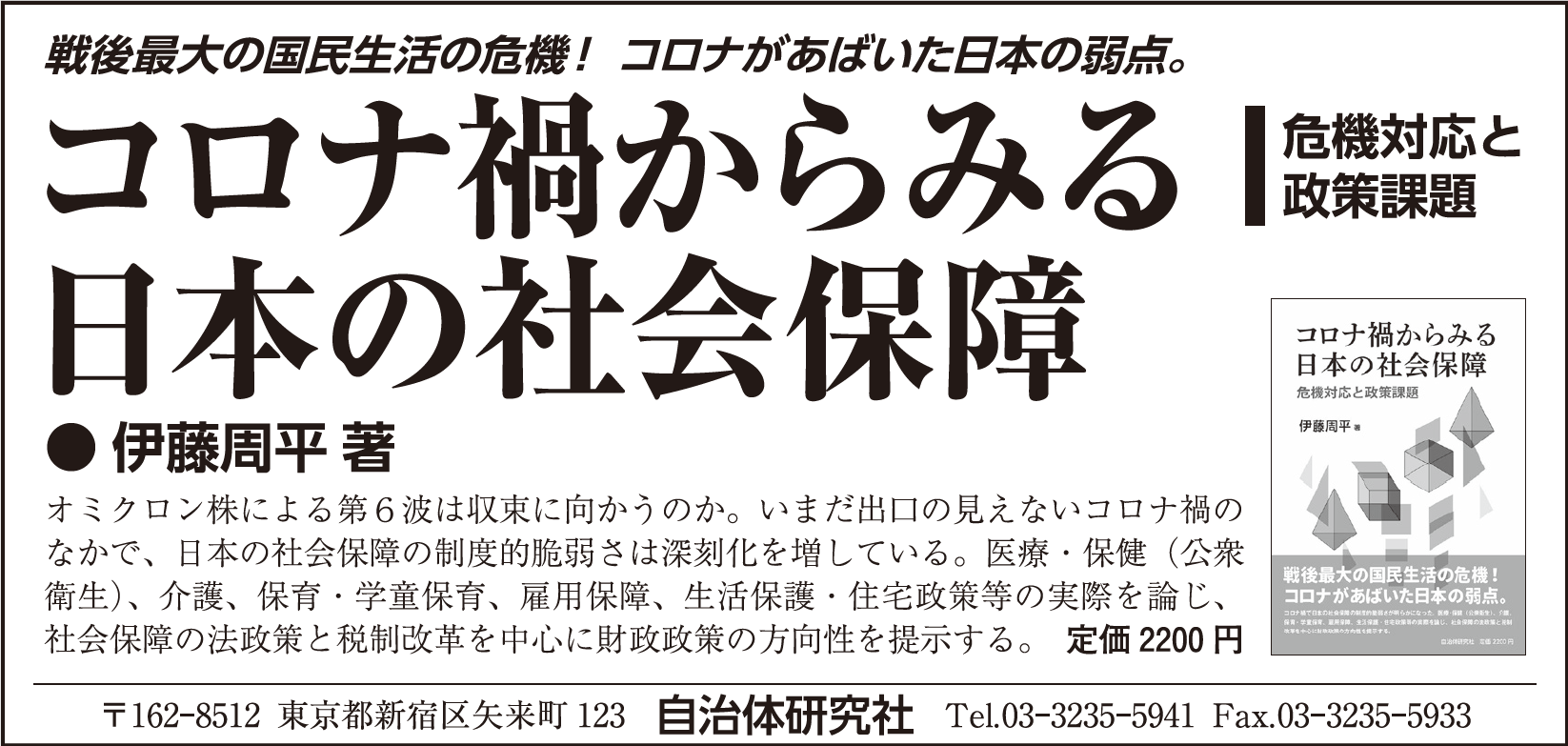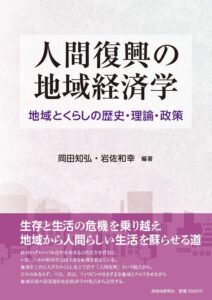コロナ禍の医療崩壊と介護現場
2020年2月以降の日本での新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、甚大な影響を及ぼし、医療など日本の社会保障の制度的脆弱さを浮き彫りにしました。
感染拡大の波は、すでに7度にわたり繰り返され、感染拡大地域では、病床や医療従事者の不足で、多くの感染者が自宅療養を余儀なくされました。そして、自宅療養の感染者への保健所等の対応が追い付かず、実質的に「自宅放置」となり、自宅療養中や入院調整中に重症化し死亡する人が続出しました。本来であれば救える命が救えない「医療崩壊」が生じたのです。
とくに2022年7月からのオミクロン株の派生株BA.5の爆発的感染拡大による第7波では、重症化しても入院できず医療が提供されない医療崩壊が繰り返され、それに伴い、死亡者数が急増しました。もともと、死亡リスクの高い高齢者数が世界最高水準にある日本では、第7波で、新規感染者数が最大で全国で1日26万人を超え、7月末から8月半ばまで5週単位で世界最多を記録、死者数も世界最悪水準となり、日本人の平均寿命が男女とも下がりはじめる事態にまで至りました。こうした緊急事態になっても、政府は、国民に感染対策を呼びかけるだけの無策に終始しました。2022年11月末まで累計5万人近くを数える、新型コロナによる死者数の何割かは、入院病床と医療従事者の不足による医療崩壊で、必要な医療が提供されず手遅れにより、つまり政府の無策・失策(いわば人災)により失われた命(多くは高齢者)ではなかったでしょうか。
一方、慢性的な人手不足にみまわれ、低く据え置かれた介護報酬で制度基盤が脆弱な介護現場は、新型コロナの感染拡大で深刻な事態に直面しました。本稿では、介護保険における給付抑制政策が、介護現場の人手不足とコロナ禍での困難を引き起こしたことを明らかにし、安心できる介護保障に向けての課題を探ります。
低く据え置かれた介護報酬と政策的帰結としての人手不足
介護事業所や介護保険施設などに支払われる介護報酬は、3年ごとに改定されますが、消費税増税にともなう2014年、2019年の臨時改定を除く、2018年度までの本改定のうち、名実ともに引き上げとなったのは、2009年度の改定(プラス3・0%)のみで、あとはマイナス改定、もしくは実質マイナス改定です。直近の2021年度の介護報酬改定は、全体で0・7%のプラス改定となりましたが、0・7%のうち0・05%は、新型コロナに対応するための感染対策の経費とされ(特例的評価)、2021年9月末で終了していますので、コロナ対応分を除けば、わずか0・65%のプラス改定にすぎません。
2012年度の改定からは、加算による政策誘導の流れが強められ、加算の算定が困難な小規模事業所の差別化を加速させ介護事業所間での格差が拡大しました。介護保険がはじまってから基本報酬は平均で20%以上も下がっており、居宅介護支援事業に至っては、介護保険開始以来、事業の収支差率が一度もプラスになったことがありません。
こうした給付抑制政策=介護報酬の引き下げに、新型コロナの感染拡大の影響が加わり、老人福祉・介護事業の倒産件数は、2020年には118件と過去最多を記録しました(東京商工リサーチの調査。以下の数値も同じ)。2021年の倒産件数は、政府の支援策の効果で、2020年に比べ81件と減少したものの、2022年の倒産件数は、1月から9月までで、すでに100件にのぼっており、政府の支援策の効果が薄れつつあることに加え、食料品価格や光熱費などの高騰によりコストが増大しており、過去最多を更新することが確実視されています。
介護報酬の抑制は、介護事業所で働く介護職員の賃金の抑制につながっています。介護報酬で特別の加算を設けても、加算を算定できる事業者は限られていること、基本報酬が抑制されていることなどのため、介護職員の基本給の引き上げにまで回っていないのです。また、介護現場で多くの割合を占める非正規・パート労働者の賃金は、介護保険制度開始以降、ほとんど横ばいです。
給付抑制政策(=介護職員の賃金抑制)は、その当然の帰結として、介護現場の深刻な人手不足を加速させ、介護現場の労働を一層過酷なものとし、介護職員を疲弊させ、働き続けることを困難にしています。介護の仕事は、ある程度の経験と技能の蓄積が必要なのですが、必要な経験を積む前に多くの職員が仕事を辞めてしまっており、介護の専門性の劣化が進んでいます。すでに学生が集まらずに廃校に至った介護福祉士養成学校もあり、養成の基盤の損失も回復困難な程度に達しています。
コロナ禍による在宅介護の惨状
そして、介護の現場は、新型コロナの感染拡大で深刻な困難に見舞われました。
在宅介護では、通所介護(デイサービス)の事業所などでクラスターが発生し、休業に追い込まれるなど、経営に大きな影響を与えました。また、感染拡大時の高齢者の利用控えや事業者側での受け入れの自粛などで、通所系サービスを中心に介護事業所は大幅な減収となりました(いまだに利用者がコロナ前の水準に戻っていない事業所も少なくありません)。とくに、2022年の第6波・第7波では、感染力の強いオミクロン株の拡大で、介護職員の感染や濃厚接触者になる事例が激増、ぎりぎりの人員体制で行っている小規模の事業所では、勤務体制が組めなくなるところも出ました。それでなくても、各事業所では、検温、換気、消毒作業などの業務負担が増え、感染に対する不安や家族の反対を理由とした職員の退職も発生し、現場の人手不足に拍車をかけています。
また、訪問介護を利用している要介護高齢者が陽性となる事例も増大しました。厚生労働省は、ヘルパーが陽性者の訪問介護に出向いた場合、職員の割増分の賃金などの助成を受けることができるとし、人繰りの関係で対応が難しい場合などには、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して別の事業所を手配するよう求める通知を出したのですが、人手不足の中、別の事業所の手配も困難な状況でした。
コロナに感染していない在宅の要介護高齢者の状況も深刻です。一人暮らしの高齢者や老老介護の世帯、認知症高齢者のいる世帯では、コロナ禍によるサービス提供の中止や外出自粛で、認知症の進行や身体機能の衰えが起き、家族介護者の負担が増大しています。
クラスター相次ぐ高齢者施設
高齢者施設では、新型コロナのクラスター(感染者集団)発生が相次ぎました。2022年8月15日から21日の期間には、高齢者施設でのクラスターの発生件数は、全国で850件と過去最多を記録しました(厚生労働省発表)。特別養護老人ホームなど高齢者施設に入所している要介護者の多くは基礎疾患をもっているうえ、感染症対策が脆弱なため、第7波での高齢者施設でのクラスターの多発は、死亡者数増加の大きな原因となりました。
医療崩壊が生じている地域では、病床の不足で、重症化のおそれのある要介護の高齢者が感染しても入院できない状況が続きました。また、入院患者に要介護の高齢の感染者が増大し、看護師の介護負担が増大するとともに、症状が回復しても自宅療養が難しい高齢者が多く病床が空かない状態が生じました。そのため、厚生労働省は、酸素吸入が必要なく症状が安定していれば、入院4日後を目安に自宅療養への切り替えを検討するよう推奨、高齢者施設に医師や看護師を派遣し、高齢者施設内の医療体制を強化して早めの退院や施設内療養を促しました。しかし、医療機関と同様の感染対策を施設内で講じることは難しく、この政府方針は、高齢者施設でのクラスター発生の増加をもたらす結果となりました。
厚生労働省は、陽性者の個室への隔離やゾーニング(他の入所者との生活空間の区分け)の実施、陽性者を担当する介護職員の固定などを求めていますが、現在の職員配置基準や施設の構造、さらに深刻な人手不足で、これを実践することはほとんど不可能でした。また、施設入所の認知症や精神疾患をもつ高齢者が陽性者となった場合、隔離や感染対策の必要性が理解できないため、対応は困難を極めました。
厚生労働省は、陽性者が入所し続ける場合は、原則すべての入所者への検査の徹底を求めましたが、PCR検査の試薬が不足し、検査の実施も追いつきませんでした。そもそも、オミクロン株の感染爆発の兆候が見え始めた2022年1月から定期的、頻回の検査を職員や入所者に行っていれば、これほどクラスターが多発することはなかったでしょう。
職員の感染も激増し、出勤停止が続出、ただでさえ人手不足の現場では、感染対策で膨れ上がった業務が回らず、職員の長時間労働が深刻化しました。入所者の入浴回数を減らさざるをえないなどサービスの質の低下が目立ち、急激な感染拡大で、介護の体制が組めなくなり、やむえず、陽性が判明した無症状の職員が、陽性の入所者を介護せざるをえなかった高齢者施設もあったといいます。施設で感染者が出た場合には、感染対策の費用負担、新規利用者の中止や施設の一部閉鎖、併設の訪問介護事業所の閉所などの対応に追われ、施設側が大きな出費を余儀なくされ、施設経営を圧迫する事態となりました。
当面の課題
コロナ禍のもと、介護現場が直面している困難に対して、当面の課題として、以下のような対策が必要です。
第1に、高齢者施設のクラスター発生を防ぐため、介護労働者や施設入所者などに対して定期的なPCR検査(少なくとも週1回)を全額国庫負担で実施する必要があります。
第2に、高齢者施設でクラスターや感染者が発生した場合には、感染者をただちに入院治療に移し、それにともなう減収、利用者の減少に伴う損失の経済的補填、人的支援を行うべきです。そもそも、高齢者施設では医療機関のような感染症対策を講じることが困難です。感染した高齢者が全員入院できるだけの臨時の医療施設を設置するなど医療提供体制を整備する必要があります。
第3に、感染者の発生していない介護事業所に対しても、利用者の減少などに伴う減収を公費で補償すべきです。
安心できる介護保障の仕組みに向けて─介護保険から介護保障へ
もともと、介護保険は介護保険料と介護給付費が直接連動する仕組みです。介護保険施設や高齢者のサービス利用が増え、また、介護職員の待遇を改善し人員配置基準を手厚くして、安心できる介護を保障するため介護報酬を引き上げると、介護給付費が増大し介護保険料の引き上げにつながる仕組みなのです。介護報酬単価の引き上げは、1割の利用者負担の増大にもはねかえります。
そして、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の高齢者)の保険料は、所得段階別とはいえ、定額保険料を基本とするため低所得の高齢者ほど負担が重いうえに、月額1万5000円以上の年金受給者から年金天引きで保険料を徴収する仕組みです(特別徴収)。どうみても、保険料の引き上げには限界があります。結果として、保険料の引き上げを抑制するために、給付抑制政策が法改正のたびにとられてきましたし、それは現在も続いています。
いまや介護保険そのものが、給付抑制と負担増の連続で、保険料を払っても給付がなされない「国家的詐欺」(伊藤周平・日下部雅喜『新版・改定介護保険法と自治体の役割-新総合事業と地域包括ケアシステムへの課題』自治体研究社、2016年、141ページ)と称されるまで、制度としての信頼を失っています。介護保険法は廃止し、自治体の責任で高齢者や障害者への福祉サービスの提供(現物給付)を行う税方式の総合福祉法を制定すべきです(総合福祉法の構想について詳しくは、障害者生活支援システム研究会編『権利保障の福祉制度創設をめざして-提言・障害者・高齢者総合福祉法』かもがわ出版、2013年、第3章(伊藤周平執筆)参照)。また、介護保険の給付のうち、訪問看護や老人保健の給付などは医療保険の給付に戻すべきです。ただし、その場合は、医療保険の負担が増えるので、それについては、公費負担や事業主負担の増大により対応していくべきです。
コロナ禍で明らかになった介護保険の問題点を踏まえつつ、安心できる介護保障に向けて、介護保険の代替案を含め、改善を求めていく取り組みを進めていくことが重要になっています。