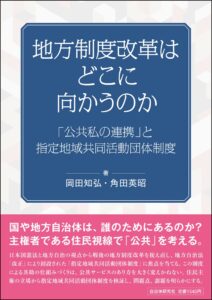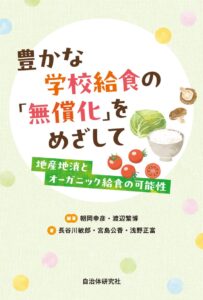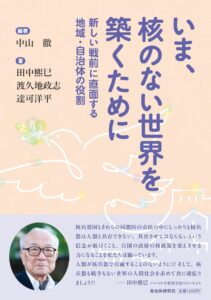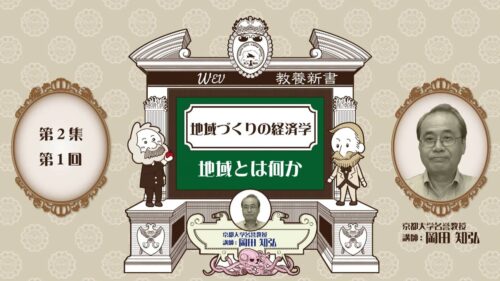岡山県吉備中央町の水道水から国の暫定目標値の20倍を超すPFASが検出されたことが発覚してから、2024年10月で1年が経過しました。汚染発覚直後から住民が求めていた公費での血液検査がようやく始まろうとしています。
血液検査を求めてきた住民団体「円城浄水場PFAS問題有志の会」(以下、有志の会)は、目下の目標としてきたことが一つ達成されたことになりますが、健康フォローアップや除染、汚染原因の企業に対する責任の追及など、課題は続きます。
汚染が発覚した当時、私は一住民としての立場から、血液検査と継続的な健康診断の実施、PFASが確認されていた3年前からの水道料金返還を求める署名活動を始めました。その後、有志の会の仲間たちとともに活動を続け、2024年9月の町議会議員選挙を経て、町議となりました。今後は議会を通して、また有志の会と連携して住民とつながりながら、安心と安全を取り戻していきたいと考えています。
これまでの経緯
現在、PFASは水質基準に含まれておらず、管理目標設定項目という位置づけです。水質検査の実施は求められているものの、義務ではありません。検査を行っていない自治体もあるなか、吉備中央町は2020年から測定をしていました。町民の約10%にあたる約1000人に水を供給する円城浄水場では、この時すでに、800ナノグラム/リットルのPFASが検出されていました。しかし、町は県への報告と対応を怠ってきました。2023年10月、汚染が発覚すると、住民に1カ月間の水道水の飲用中止を呼びかけ、取水源の切り替え作業を行いました(詳細は『住民と自治』2024年11月号をご参照ください)。そして、町は専門家による三つの委員会を設置し、健康影響の対策、汚染の原因究明、発覚までの不作為に対する原因究明について、調査・議論を行いました。また、2024年3月、血液検査・健康フォローアップの実施を発表するまでの間に、5回の住民説明会を開催しました。
有志の会ができるまで
住民説明会は、水道水の飲用中止が始まった翌日の10月17日に、第1回目が開催されました。会場には約300人が詰めかけました。住民から出された疑問は主に「汚染がわかっていたのに、なぜその水を飲ませ続けたのか」、「高濃度のPFAS摂取が体にどんな影響を与えるのか」ということでした。
町は「確定的な知見はない」、「健康被害は確認されていない」と、国が示す見解を繰り返しました。住民からはPFASの血中濃度の測定を求める声が上がりましたが、これに対しても「確定的な知見がない」という回答でした。
私の席の隣には、子育て中の友人が座っていました。我が子が産まれたときから汚染した水を飲ませてきた母親の気持ちを、会場正面に座る町長や副町長が理解できているようには到底思えない対応でした。説明会は21時過ぎに打ち切られ、会場をあとにした私たちは、自分たちで何かできることはないか話し合い、署名という形で住民の怒りと不安を示すことに決めました。
私たちが署名の準備を進めていたころ、円城に家族3人で暮らす阿部さんは、持ち前の探求心と行動力でPFASについて念入りに調べていました。そして、国内のPFAS研究の第一人者で、全国各地の汚染地で血中濃度調査を行ってきた小泉昭夫先生(京都大学名誉教授)にたどり着き、相談や協力依頼をして、汚染発覚から約1カ月後に、自主的な血液検査を実現させました。
有志の会は、自らが暮らす地域でおこった汚染問題に対して各々ができることに取り組むなかで、自然に集まったグループです。関心を寄せる住民が情報交換をする場としてのスタートでしたが、その時々で必要な働きかけを相談しながらやっていこうと、有志の会が発足し、名前がつけられました。
有志の会の取り組み
署名活動に取り組んでいた頃、第2回目の住民説明会が開催されました。住民からの血液検査実施の要望に対して、山本雅則町長の回答は「専門家が決めること」の繰り返しでした。専門家とは、町が設置した健康影響対策の専門委員会を指しています。委員は大学や国立環境研究所の研究者、地元医師など9人で構成されています。専門委員会の議事録からは、血中濃度検査実施について慎重な意見が多いことがわかりました。また、9人のうちPFASの専門家と言える委員は一人だけでした。有志の会は委員の追加やオブザーバー参加の要請、座長への意見要望などの働きかけを行いました。最終的に、専門委員会の結論は血液検査の実施を推進する内容ではありませんでしたが、町は血液検査の実施を決めたことになります。
この住民説明会の後、私たちは1038筆(円城地域373筆)の署名を町へ提出しました。この時から町長は「住民に寄り添いたい」と発言をするようになりました。
そして、11月22日、第3回目の住民説明会では、専門委員会の頼藤貴志座長による、住民の過去の検診結果を用いた汚染地域と地域外の比較説明がありました。対象数が少ないために言い切れないと前置きをしつつも、調査結果から健康被害は確認できない、という内容でした。「安心材料にしたい」という町の意図だと思われますが、「血液検査をせずに沈静化させたい」という安易さも感じられました。
この数日後に、私たちは自主的に27名の血液検査を実施しました。結果は、PFOAが平均171・2ナノグラム/ミリリットルという一般住民としては世界的にも高濃度であり、汚染が深刻であることが証明されました。
この自主的検査の位置づけは、公費による血液検査を町に促すことです。被害住民が自らの血中濃度を把握し、PFAS関連疾患を中心に健康観察を行っていくこと、継続的に血中濃度を測り数値の変化を追うこと、さらには公害に対する補償という位置づけで数値を把握しておくためには、希望者全員への血液検査の実施は譲れません。また、疫学調査が遅れている日本において、高濃度汚染地での血中濃度検査は必須だと考えました。
検査後、結果を公表するための記者会見と、改めて公費での血液検査実施を求める要望を町に対して行いました。また、結果は専門委員会にも伝わるようにしました。事態の重大性を踏まえて、全国や世界に発信できるような形で記者会見は東京で行う案もありました。しかし、地元のメディアを大事にすること、そして何より重視すべきは、地域に寄り添ってこの結果と向き合うことではないかという思いから、地元での実施となりました。
また有志の会では記者会見と同時に、対象地域の全戸に対して、血液検査の結果と今後の提案などを記したお知らせを配布しました。私たちがどんな意図でこの血液検査をしたのか、結果がどんな意味を持つものか、今後どんなことが必要なのかなど、有志の会からの情報提供を行いました。
有志の会は移住者を主にした数世帯の小さな集まりです。十分とは言えなかったかもしれませんが、地域住民とのつながりを丁寧に持つことを心掛けてきました。会代表の小倉博司さんは唯一円城で生まれ育ったメンバーであり、地域からの信頼も厚く、自治会とのパイプ役も果たしてくれました。
2024年2月11日には、小泉昭夫先生、原田浩二先生(京都大学准教授)を招いた学習会を行い、住民をはじめ多くの方が参加しました。
またその頃、内閣府食品安全委員会によるPFAS評価書案についてのパブリックコメントが募集されていました。案の内容では、住民、国民の安全が守られないという危機感から、パブリックコメントへの参加を呼び掛ける取り組みも行いました。
そして2月、血液検査の実施を意識してのものと思われる飲水者調査(各戸・事業所に調査票が届き、誰が円城浄水場の水を飲んでいたかを申告する。対象者には里帰りの家族など地域外の人も含まれる)が町によって行われ、翌月3月22日には町による健康影響対策に関する方針が発表され、血中濃度測定が実施されることになりました。
血液検査の実施にあたって
3月22日に発表された健康影響対策の内容は、PFAS血中濃度測定以外には特定検診・人間ドック結果の情報収集(脂質・肝機能)、健康診断受診率向上の取り組み、早産・低出生体重児の発生割合観察、学校健診の分析、精巣がんと腎臓がん発生割合聞き取りとありました。また、予算として6120万円が計上されました。
この時、健康調査としては情報収集しか予定されていませんでした。そこで、PFAS血中濃度測定の際の採血で、脂質・肝機能・腎機能などの検査を一緒に行うことを求めました。また、腎エコー検査の実施など、特定検診項目にないPFAS関連疾患についての健診、大人だけでなく子どもに対する血中濃度測定の実施など、項目や方法などの要望を細かく伝えてきました。
9月には健康影響調査として、血液検査希望の有無と同時に、健康状態や汚染発覚当時の飲水状況の確認として調査票の提出が町より求められました。9ページある調査票の回収率は低かったため、担当の保健課職員が未提出者を個々に訪ねてまわるという取り組みを行いました。11月5日現在、回収率は80・4%、そのうち血液検査希望者は58・5%(円城浄水場区域)となっています。
11月5日には血液検査希望者への実施日程通知と検査券郵送が始まり、11月下旬から12月上旬の日程で2歳以上を対象に血液検査が実施されます。検査項目はPFAS濃度の他に、脂質検査、肝機能検査、貧血検査、成人に対してはこれらに加えて甲状腺ホルモンが入っています。交通の便が悪いため、会場までの支援も予定されています。
私たちは「吉備中央町での実施が、全国各地の汚染地自治体による血液検査にもつながって欲しい」、との思いでこれまで活動してきました。
また有志の会は、町が今後すべき重要な取り組みとして、被害住民の健康フォローアップを考えています。PFAS関連疾患を中心に早期発見・早期治療が実施できるよう町に対し求めていきます。そして、汚染原因である企業に対しては、除染だけではなく、健康被害への補償も要求していく必要があると考えています。