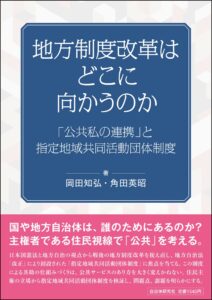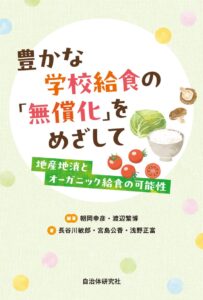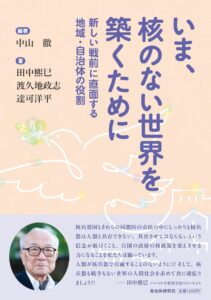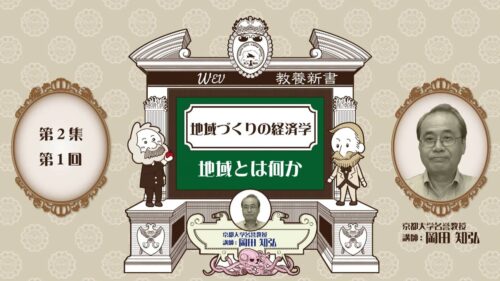被災者の運動で個人補償も含む公的支援は一部実現しましたが、生活と住まい・生業への一元的・総合的支援制度はいまだ整っていません。阪神・淡路大震災30年の教訓から今後の課題を考えます。
毎年繰り返される台風、豪雨、水害、豪雪、地震、土砂災害などの自然災害で、多くのいのちが失われ、住まいと生業が奪われつづけています。1年を迎えた能登半島地震は、30年前の阪神・淡路大震災の再来で、教訓は何ら生かされていません。被災者の生活と住まい・生業に対する一元的・総合的な支援制度がいまだに整わないことに胸を痛めます。
被災者への公的支援を求め続けて
1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、6434人の死者、4万3千余人の重軽症者、住宅全壊18万6000世帯、半壊・半焼27万4000世帯、一部損壊39万棟、被害総額10兆円という大惨事でした。
阪神・淡路大震災救援・復興兵庫県民会議(以下、県民会議)は、震災直後の1995年3月に労働・医療・婦人・青年・社会保障推進協議会・法曹界など45団体で結成、シンクタンクとして兵庫県震災復興研究センターも発足、全国への発信に大きく寄与しました。県民会議は、毎年1月17日に、メモリアル集会を開催しています。
県民会議は、1990年の長崎雲仙普賢岳の噴火災害、奥尻島を襲った1993年の北海道南西沖地震・津波災害への1000万円を超える義援金による給付を目の当たりにし、「せめて雲仙・奥尻並みの公的支援を」と「住宅・店舗再建に500万円」「生活再建に300万円」を求める署名運動をはじめ、医師会・生活協同組合・地元NGOの呼びかけによる医師会・看護協会・薬剤師会・県下大学の学長、地元マスコミ社長などによる「公的支援を求める48氏のアピール」として全国に発せられました。各界有識者・著名人による公的支援実現を求めるアピール運動は4回を数え全国に大きくひろがりました。賛同は国会議員の過半数を超えるまでになりました。
なお、この運動の中1999年、「災害被害者支援と災害対策改善を求める全国連絡会(全国災対連)」が結成されました。被災地に地方組織がつくられていますが、それを全国各地に広げ、迅速な支援と全国への発信をおこなうことが求められています。
*小田 実(おだまこと:1932~2007年。大阪生まれの作家・政治運動家。「ベトナムに平和を!市民連合(べ平連)」設立者の一人で九条の会呼びかけ人の一人。阪神・淡路大震災の被災者として、何もしてくれない政府や国会に怒りをぶつけ、市民のための市民による立法を企て政府を動かした。
「被災者生活再建支援法」の実現
阪神・淡路大震災被災地の惨状と、公的支援を求める超党派の市民・議員運動と世論の広がりによって、ようやく1998年につくられたのが「被災者生活再建支援法」です。何回もの見直しでその後住宅再建に使えるように改善されましたが、「生活と住宅再建が300万円」で困難なことは、東日本大震災、能登半島地震などでいよいよ明らかになっています。当時、「せめて雲仙・奥尻の半額・500万円の個人補償を」の願いが阪神・淡路大震災の被災地からからわき起こったのは当然でした。
公的支援実現の最大の壁は「個人補償」でした。議員立法制定を求める氏や被災者の運動で衆参国会議員による野党の法案提出に至り、世論の高まりに対し自民党は急きょ議員立法を提出し可決成立させました。公的支援・個人補償を拒否してきた厚い壁に風穴を開けたのが「公的支援100万円」を柱とする「被災者生活再建支援法」でした。その後200万円に拡充されましたが、頻発する災害が増加しているにも関わらず、300万円に引き上げられてすでに20年間据え置きです。
「災害ケースマネジメント」の徹底・拡充を
被災地では、仮設住宅ネットワーク、災害公営住宅、借り上げ住宅の環境改善、高齢者の見回り、孤独死対策、借り上げ住宅追い出し裁判、被災者ネットワーク等々、被災者の生活と生業を再建するための多様な運動が続けられてきました。
現在、被災者にたいする公的支援は、「り災証明書」にもとづく「災害救助法」と「災害弔慰金法」による弔慰金、「災害援護資金の貸付」、特別立法と「復興基金」です。生活保護・介護保険料・国民健康保険などはすべて現行法制通りで、り災証明書が支援のすべてです。資力がないにも関わらず返済を求められ続けてきた災害援護資金の貸付免除は「給付」に改善すべきです。「避難所→応急仮設→復興住宅・借り上げ住宅」という住民無視の復興計画により、直接・間接死6434人のほかに1500人近い孤独死を招いた、阪神・淡路大震災の「単線型プログラム」を改め、社会保障諸制度の全面活用による生活再建支援を保障する「災害ケースマネジメント」の徹底と拡充が求められます。
被災者支援の当面の課題
当面の課題は、①「想定外」を口実とせず初動体制を重視し、②「被災者生活再建支援法」にもとづく「支援額300万円」を住宅・生活再建に見合う額に大幅に引き上げ、半壊・一部損壊への適用を拡大、③トイレ・食事・ベッド・冷暖房など避難所環境の抜本的改善、④自宅避難者を含め被災者の生活・住宅再建に寄り添う災害ケースマネジメントの徹底、⑤地域コミュニティを維持した仮設住宅、みなし仮設住宅、借り上げ住宅の確保、⑥り災証明書にもとづく被災者生活再建支援にとどまらず、生活保護法をはじめとする社会保障の全面的適用による生活・生業の再建支援の徹底、⑦災害援護資金、緊急災害復旧資金など各種融資の利率や償還期間の特例改善、⑧道路・電気・上下水道・港湾などのライフラインの整備、⑨前例のない災害には前例のない対応のため防災計画・避難計画の見直し、を求めるべきです。
さらに、南海・東南海トラフ地震に備え、「被災者生活再建支援法」、「災害救助法」、「災害弔慰金法」の不十分な支援を拡充するものとして、京都府や鳥取県をはじめ多くの府県で行われている自治体独自の「被災者生活再建支援制度」を創設・恒久化することです。また、自治体の行政改革による職員の際限のない定数削減を中止し、防災体制を強化すべきです。
「創造的復興」からの転換を
阪神・淡路大震災の被災地では、被災者の生活と生業を二の次にした「創造的復興」の名のもとに神戸空港建設、神戸港整備、副都心の再開発、地下鉄「海岸線」建設など鉄とコンクリートによる巨大事業が強行されました。西部副都心・神戸市長田区新長田駅南の再開発は40棟の高層ビルを建設する計画で、29年目にしてようやく完成したものの、人口減少下、ビルと一体化して再生した大正筋商店街なども、閑散として「シャッター通り」と化しています。
東日本大震災でも、守るべき集落のない総延長400キロを超える巨大防潮堤、造成完了が限界集落をつくった「高台集団移転」など、「創造的復興」の名による惨事便乗型の巨大開発による復興計画の問題点が明らかになり、被災者の生活保障を二の次とする政府の姿勢がリアルに示されています。
被災地・被災者が求めているのは、被災者の人権と尊厳ある暮らし・生業の再建です。「創造的復興」の名による自己責任論、惨事便乗型復興災害、コミュニティを破壊する「コンパクトシティ」化による棄民政策をあらため、住み続ける権利と人権保障、平和的生存権を守ることが求められています。
幾千、幾万のいのちが奪われてもなお被災者のねがいが届かない、この国の政治のありようを変えることは、生かされた私たちの責任です。
公的支援の到達点、教訓を伝えつづけて
東日本大震災、熊本地震、能登半島地震をはじめ、地震・災害列島のわが国では地震・台風・豪雨・豪雪・火山噴火等々が毎年のように続いています。災害列島に住み暮らしている我々にとって、「被災者生活再建支援法」はまさに命の綱ともいうべき重要な法律です。この法律の制定過程を振り返れば、被災者の運動なくしてはこの法の実現はありませんでした。法改正もまた闘いです。
災害は常にローカルであり、時とともに忘れられてしまいます。そのために求められることは、被災地の実情、被災者の願いを全国に発信し、公的支援の到達点、教訓を繰り返し伝えつづけることです。被災者と国民生活に苦難を押し付け、財界の利益を再優先する自・公政権の暴走政治ストップの世論と運動に、阪神・淡路大震災30年の教訓が生かされることを願うものです。