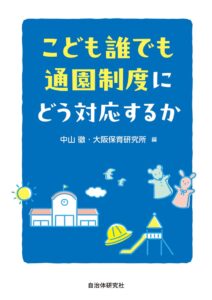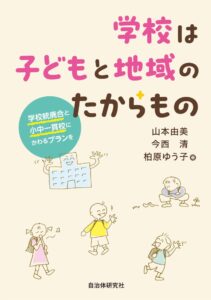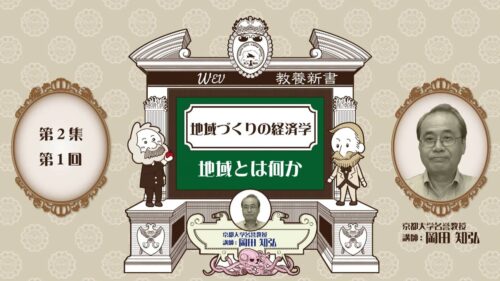コロナ対応にみる法と民主主義
書籍の内容
コロナ禍とデジタル化のもと、見つめ直すべきは民主主義と地方自治のあり方である。
パンデミックに便乗して、立憲主義・法治主義を掘り崩す政策が頻発している。
国家は人びとの「命と暮らし」守っているのか。地方自治体、地方議会は、その役割を果たしているのか。
さまざまな事象を法と民主主義の観点から詳細に分析して、地方自治と民主主義の可能性を追究する。
国家は人びとの「命と暮らし」守っているのか。地方自治体、地方議会は、その役割を果たしているのか。
さまざまな事象を法と民主主義の観点から詳細に分析して、地方自治と民主主義の可能性を追究する。
目次
はしがき
第1章 立憲主義・民主主義からみた日本のコロナ対応
はじめに
1 憲法からみたコロナという「危機」
- (1)「危機」の類型
- (2)コロナという「危機」と憲法
2 コロナ対応を検証するための視点─立憲主義と民主主義・権力分立
- (1)基底的原理としての立憲主義
- (2)国民主権原理と権力分立
3 国によるコロナ対応を検証する
- (1)国際的状況
- (2)国会による民主的統制
- (3)司法的統制
- (4)問題の背後にあるもの
- (5)立憲主義の日本モデル?
4 改憲による緊急事態条項追加?
- (1)感染症対応のための緊急事態条項追加改憲論
- (2)日本国憲法における国家緊急権規定欠如の意味
- (3)自民党「改憲4項目」における緊急事態条項
- (4)コロナ対応に緊急事態条項追加は必要か?
おわりに
第2章 コロナ禍の下での人権保障
はじめに
1 「コロナと人権」総論
- (1)現象形態としての「コロナと人権」
- (2)社会構造としての「コロナと人権」
2 日本型感染対策の構造と日本型人権侵害の態様
- (1)「要請」と「自粛」
- (2)「公表」と「立入り」
- (3)日本型コロナ対策の問題点
- (4)「補償」か「保障」か
3 コロナ禍の下での差別・排除
- (1)公権力による不平等扱い禁止と社会的な差別・排除抑制のための公権力の責任
- (2)給付金事業からの特定業種の排除
- (3)ハンセン病差別の教訓と感染症法の理念の変容
- (4)自治体条例における差別防止の取組み
おわりに
第3章 コロナ下の地方議会と条例
はじめに
1 地方議会の対応
- (1)地方議会の開催と出席者の限定
- (2)オンラインの活用
- (3)住民からの意見聴取
2 地方議会と首長
- (1)専決処分と臨時会
- (2)要望書、意見書等の提出
- (3)特別委員会等の設置とコロナ対策の検証
- (4)給与・報酬の削減、寄付の強制と給付金給付公約
3 コロナ対策条例
- (1)条例制定状況
- (2)コロナ対策条例の内容
- (3)条例制定とパブリック・コメント
おわりに
第4章 分権型行政から集権型行政への転形と法治主義および地方自治の危機
─コロナ対応から考える─
はじめに
- (1)行政改革会議の「最終報告」
- (2)例外状況への対応を目的とするとき、内閣・内閣総理大臣は法治主義から解放される─法治主義の危機
- (3)例外状況への対応を目的とするとき、集権型行政への転形が起こる─地方自治の危機
1 例外状況におけるコロナ対応は、法治主義の没落をもたらすか
- (1)C.シュミットと「外典上の主権行為」(apokrypher Souveränitätsakt)
- (2)法治主義の原則がはずれ法から解放された内閣および内閣総理大臣のコロナ対応
2 集権型行政は適時適切なコロナ対応を保障するか
- (1)トップダウンの集権型行政によるコロナ対応に関する議論の登場
- (2)法定受託事務とその処理基準
- (3)厚労省が定めたPCR検査等実施基準
- (4)PCR検査等実施基準に従った検査とそれがもたらしたコロナ対応の悲劇的失敗
3 法治主義および地方自治の危機とその再生の徴候
- (1)法治主義と地方自治の危機
- (2)危機にあって法治主義と地方自治の後退を勧めるC.シュミットの視角
- (3)C.シュミットの視角に替えてK.マルクスの弁証法的視角から危機をみる─法治主義と地方自治の再生の徴候をみる
- (4)学校休業を市町村の判断に委ね、内閣総理大臣による法治主義の後退を阻んだ知事の登場
- (5)法定受託事務の「殻」を突破する知事の登場
おわりに
第5章 分権型行政から集権型行政への転形と法治主義および地方自治の危機
─デジタル化対応から考える─
はじめに
- (1)ロッキード事件丸紅ルート最高裁判決
- (2)喫緊の行政需要への対応を目的とするとき、内閣・内閣総理大臣は法治主義から解放される─法治主義の危機
1 デジタル化という喫緊の行政需要への対応は、法治主義の没落をもたらすか
- (1)デジタル化による資本主義の「突然変異種」(mutant)の出現─監視資本主義(surveillance capitalism)への転形
- (2)デジタル化という喫緊の行政需要への対応が必要となるとき、行政は法治主義から解放される─法治主義の危機
2 デジタル化という喫緊の行政需要への対応は、地方自治の没落をもたらすか
- (1)デジタル化という喫緊の行政需要があるとき、それへの対応の「必要は地方自治をもたない」(necessitas non habet loci autonomiam)
おわりに
- (1)二つの異なる目的と共通の手段でみるパラダイム
- (2)テクノロジーを「技術的なもの」(technicity/Technizität)と「駆集用立ての挑発システム」(frame/Ge‐stell)としてみると、何がみえてくるか?
- (3)「主権的なもの」=「政治的なもの」としての「技術的なもの」および「駆集用立ての挑発システム」