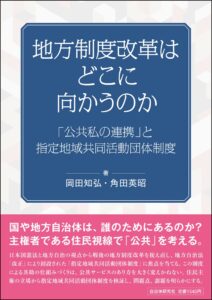最低賃金と公務員労働者の不条理
春闘が後半戦に入った時点での、全労連や連合の回答集計では、昨年水準を上回り賃上げ基調にあることは見てとれます。しかし、一方で新型コロナ禍からの世界的な需要回復とロシア軍によるウクライナ侵略の影響、日銀の超低金利政策の継続を要因とした円安進行で、物価は急激な上昇を示しています。「消費税3%増税に匹敵」という物価上昇に対して、2%あまりの賃金引き上げでは、賃上げ分は帳消し、実質賃金の低下は必至です。春闘後半戦は、交渉を継続している民間労組と連帯し、最低賃金(以下、最賃)の全国一律・大幅引き上げと、人事院勧告に向けた民間調査を開始した公務員賃金引き上げを中心に賃上げ基調を定着・前進させることが必要です。特に新型コロナ禍で生活困窮の広がりが浮き彫りになっているもとで、最低賃金を大幅に引き上げ、「生計費」に見合った水準にしていくことが急務です。そのための中小企業に対する支援策の実行も不可欠です。
厚生労働省「令和2年最低賃金に関する基礎調査」(2020年)では、神奈川県の最賃改定のは8.8%。全国平均4.7%を上回り、青森、宮崎、秋田に次ぐ水準です。同時に指摘しなければならないのは、民間事業所で働くパートやアルバイトといった非正規労働者に限らず、実は自治体公務職場に最賃水準で働く労働者=会計年度任用職員が多数存在している実態です。昨年も10月の最賃改定に伴い、労働組合で点検と当局交渉などを行い、多くの自治体が賃金=報酬額の改定を行いました。しかし、労働組合がない、ある自治体当局は、「法施行前は特別職非常勤職員だったので、最賃改定に準じて報酬額を改定していたが、法施行後は一般職の会計年度任用職員になったことから最賃規程の適用除外なので報酬額は改定しない」と驚くべき姿勢を示しました。一般職公務員として正規職員と同様の義務を負わせながら、また、現実に自治体行政の不可欠な担い手として職務に従事させながら、「労働条件の改善、生活の安定、労働力の質的向上」(最低賃金法)は不要とでもいうのでしょうか。
そもそも少なくない自治体が準拠している国家公務員の高卒初任給(15万600円)が、時間額(国家公務員の算定式)で897円であり、神奈川県の最賃1040円はもとより、2021年改定の全国加重平均930円をも下回ったままにされていることに根本的な問題があるといえます。労働基準法(以下、労基法)にもとづく時間額の算定式を用いても神奈川県下で言えば、10%の地域手当が支給されなければ、高卒新規採用職員は3年程度、最賃以下で働くことになるのです。「常勤職員の属する職務の級の初号給を基礎として」決定される会計年度任用職員の報酬額が前述のような水準になるのは必然です。
労基法第1条は、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」とし、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」としています。労基法が原則適用される地方公務員はもちろん、この趣旨は国家公務員においても尊重されるべきものです。労働関係の一方の当事者として、自治体当局も人事院・人事委員会も不合理の解決に真剣に向き合うべきではないでしょうか。