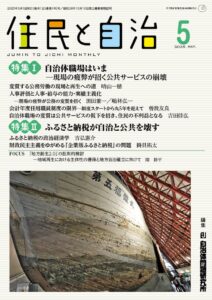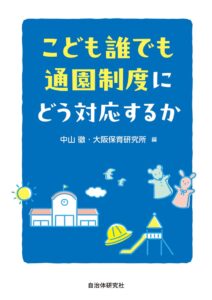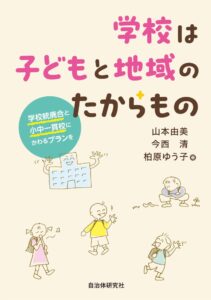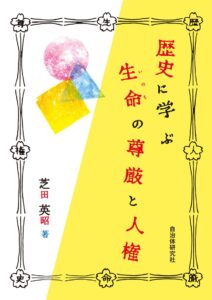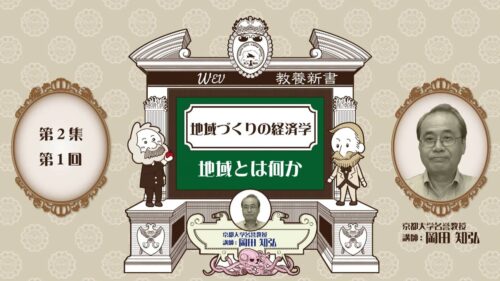いま、自治体職員をめぐるハラスメントは社会的に大きな問題となっています。
とりわけ、職員へのパワハラ、業者へのおねだり、寄付金集めのための不正な補助金増額といった疑惑に加え、それらを公益通報した幹部職員及び補助金を担当した職員を自死に追い込んだとされる兵庫県知事を許すことはできません。このような首長によるハラスメントをはじめ、自治体の組織内部におけるハラスメントを防止・根絶することが求められていることは言うまでもありません。
同時に、もう一つ問題になっているのが、自治体職員に対する「カスタマーハラスメント」です。窓口対応において、「侮蔑や大声で威圧するなど乱暴な言動」を浴びせられたり、「窓口や電話で長時間の拘束」を強いられたり、「行政手続き等への不当な要求」を迫られることが、自治体職場でも大きな問題となっています。暴言を浴びせられた職員が精神的不調に陥ったり、退職を余儀なくされる事態まで生じています。暴力に至らなくとも、脅迫や不当要求から自治体職員は守られなければなりません。
一方で、自治体におけるカスタマーハラスメント防止が「行き過ぎ」となり、住民の正当な権利行使をカスタマーハラスメント扱いしたり、住民運動を萎縮させることはあってはなりません。しかし、「住民への説明では同意を得る必要はない」、「必要に応じて発言時間に制限を設ける」といった行き過ぎた対応も生まれています。
東京23区のある区議会において、小学校の改築をめぐる住民説明会が深夜に及んだことについて問われた区幹部職員が「東京都では公務員に対するカスタマーハラスメント防止検討等、そういう検討も始めている」と言及しました。これに対して、「区民にカスハラのレッテルを張るのか」などと批判が上がり、住民側も「活動の萎縮につながりかねない」と危惧する報道がされました(2024年5月7日付『東京新聞』TOKYO Web)。
ところが、このようなもとで、2024年10月、東京都は全国初のカスタマーハラスメント防止条例を制定しました。「条例案では何がカスタマーハラスメントに該当するか明確でない」と慎重な審議を求める声に対して、小池百合子知事は「カスタマーハラスメントを、顧客等からの著しい迷惑行為であり、就業環境を害するものと定義づけ、全ての人を対象に、その禁止を明示する」と説明。「正当な権利に基づく行為が不当に阻害されることがあってはなりません」とは言うものの、「現場で生じるさまざまなハラスメントを防ぐには禁止行為の範囲を狭く捉えず」、「条例の考え方を解説する指針を示し、現場における正しい運用を促す」にとどまっています。
条例は都庁や区役所をはじめ自治体職場も対象です。民間企業なら「顧客を選ぶ」こともできますが、自治体職員は「住民を選ぶ」ことができません。住民からみても、民間企業が提供するサービスに不満があれば他の企業のサービスを選択できますが、自治体が提供する住民サービスに不満があっても、他の自治体が提供する住民サービスを選択することはできません。民間企業の従業員とは異なり、憲法が定める「全体の奉仕者」である自治体職員は住民の正当な権利行使に応える責務があることを忘れてはなりません。