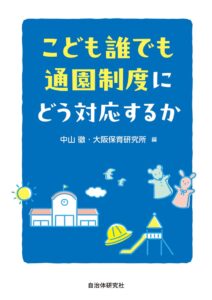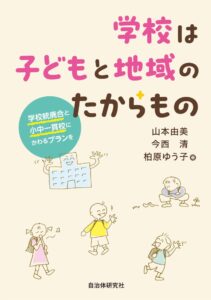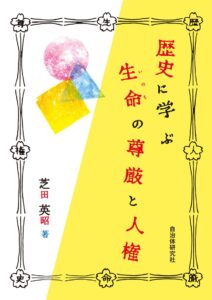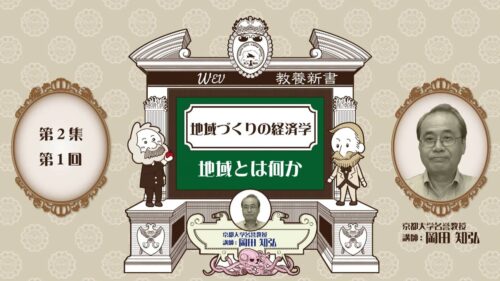私は、公立保育所で三十余年、保育士として勤務しました。1990年、入庁当時の私に先輩たちは、「子どもは生まれてくるところを選べない。だから憲法には様々な国民・住民の権利が定められている。その権利を保障することが自治体とそこに働く自治体労働者の役割だ」と教えてくれました。あれから30年以上が経過した現代の社会はどうなっているのでしょうか。格差と貧困は今もなお拡大し、憲法が定める国民・住民の権利が保障される社会になっているとはとても思えません。
さて、能登半島地震から1年余りが経ちました。自らも被災者である自治体労働者が、懸命に住民のいのちとくらしを守るために今も働いています。被災自治体を支援する自治体も深刻な人員不足が続き、長時間労働も蔓延しています。私も輪島市、珠洲市の災害支援ボランティアに参加しましたが、時計の針が止まっているかのように、民家、集落が瓦礫に埋もれたままの状態が続いています。経済効率最優先の「創造的復興」、地域を丸ごと切り捨てる「集約的なまちづくり」によって、住民本位の復旧・復興は遅々として進んでおらず、国民・住民の権利が守られていません。
一方、自治体のアウトソーシング(民営化・民間委託等)によっても国民・住民の権利が侵害されています。2023年9月、全国で給食調理業務などを展開している「ホーユー」(広島市)が、各地で給食の提供を突然停止しました。この問題が起きた主な要因には、コスト削減を最優先に進めてきた自治体のアウトソーシングがあります。低賃金、不安定雇用の労働者の犠牲のうえに成り立たせてきた自治体のアウトソーシングが、昨今の物価高騰によって破綻したのです。そこには、食育の視点、人権保障の視点が完全に抜け落ちています。そしてその犠牲となるのが、子ども、高齢者、障害者など住民なのです。
このような状況に直面するたびに、私は自治体とそこに働く自治体労働者の役割について考えます。そこには、かつて先輩たちが教えくれた「憲法が定める国民・住民の権利保障」ともう一つ、「地域(単にエリアだけでなくコミュニティーも含む)づくり」があると思うのです。それは、住民が共に励まし合い、協力し合って、誰もが安心して暮らすことができる地域をつくっていくこと、住民自治を育むことです。そこでは、主権者としての住民の成長・発達保障と、共に地域をつくっていく自治体労働者の成長・発達も保障されなければなりません。
「憲法が定める国民・住民の権利保障」と「地域づくり」、これが私なりに考える自治体とそこに働く自治体労働者の役割です。私はこのことを公立保育所を守る住民との共同の運動から学びました。
さて、この間、自治労連は、「国民・住民の手に公共を取りもどす」運動に取り組んでいます。この運動の前進に向けては、自治体とそこに働く自治体労働者の役割を発揮することはもちろん、公共を支える公務公共体制の拡充、働きがいと魅力ある職場をつくる運動も重要です。また、職場や地域での自治研活動、自治体問題研究所との連携も大切です。これからも自治体労働者として、先輩たちの思いを受け継ぎ、住民のいのちとくらしを守り、誰もが安心してくらすことができる地域社会づくりに奮闘したいと思います。