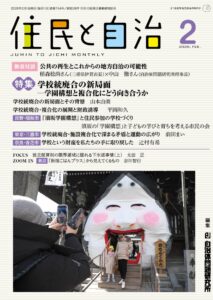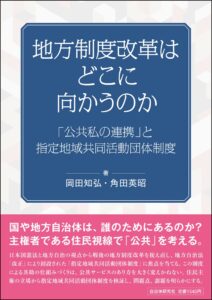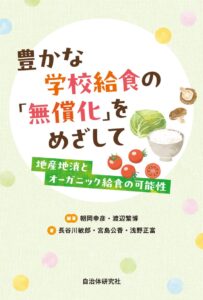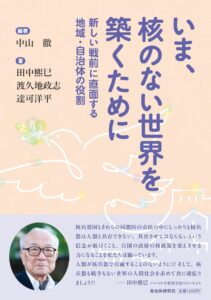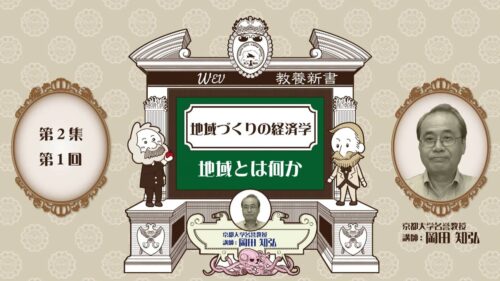月刊『住民と自治』 バックナンバー2025年
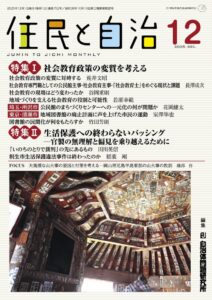
- 2025年12月号
- 特集Ⅰ 社会教育政策の変質を考える
特集Ⅱ 生活保護への終わらないバッシング─無理解と偏見を乗り越えるために - 戦後社会教育は、主権者となった住民の学習権を保障し、民主主義の担い手の育成をめざしてきました。しかし、公民館が教育委員会から首長部局 のもとへと移されたり、図書館運営が民間の指定管理者にゆだねられたりして、社会教育は地域課題解決支援へと矮小化されつつあります。特集Ⅰは、変質する社会教育政策に光を当てます。また、2025年は生活保護行政をめぐる大きな動きがありました。桐生市生活保護違法事件に対する第三者委員会の報告書が発表され、「いのちのとりで裁判」では最高裁において画期的とされる判決が下されました。一見、生活保護制度の運用は是正に向かっているかにみえます。しかし、はたしてそうなのでしょうか。特集Ⅱではバッシングや違法行為が生まれる背景を考えます。
- 2025年11月15日 発売
- ¥800(税込)
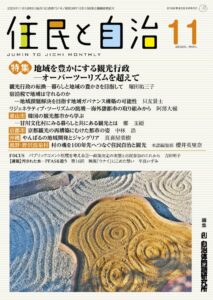
- 2025年11月号
- 特集 地域を豊かにする観光行政─オーバーツーリズムを超えて
- 日本政府が掲げる「観光立国」のもと、2024年には訪日観光客数と旅行消費額が過去最高を記録しました。 しかしその陰で、観光都市ではインバウンド需要を見込んだ過度な施設整備や外部資本への依存が進み、地域の実情や住民の声が十分に反映されない場面もあります。 本来、観光は地域の自然や文化、住民の暮らしに根ざし、持続的な発展を支える営みです。 本特集では、宿泊税や国内外の地域ガバナンスの比較、リジェネラティブ・ツーリズム(再生型観光)、住民自治の実践などを通して、「地域を豊かにする観光行政」とは何かを問い直します。
- 2025年10月15日 発売
- ¥800(税込)

- 2025年10月号
- 特集Ⅰ 第67回自治体学校 in 東京から 特集Ⅱ 危機に立つ公的医療保険制度
特集Ⅰでは、2025年7月26日・27日に開催した第67回自治体学校in東京の概要を報告します。戦争できる国づくりへの暴走が加速するなか、「ともに学ぶ 地方自治が切りひらく平和で豊かな社会」をメインスローガンに掲げ、“みんなが先生 みんなが生徒”となって、平和と地方自治の意義・役割を学び合いました。本特集では、中山徹氏による基調講演「戦争できる国づくりと自治体の役割」をはじめ、「地域と自治体 最前線」と題した4名の報告者によるリレートーク、分科会概要(第1、第6、第7、第10分科会)を報告します。
特集Ⅱでは危機に立つ公的医療保険をめぐる現況と新たな搾取などについて考えます。今夏の参院選では「現役世代の社会保険料負担軽減」を複数の政党が掲げました。国民皆保険の維持に不可欠な公的医療保険制度が財政難や制度改変により揺らぐ現状において、国民健康保険の構造的課題や、マイナ保険証問題を含め、社会保障の根幹を守るための政策課題と展望を考えます。
- 2025年9月15日 発売
- ¥800(税込)
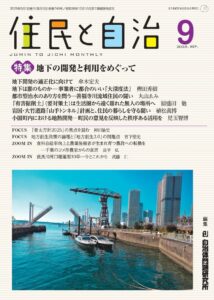
- 2025年9月号
- 特集 地下の開発と利用をめぐって
- トンネルや地下鉄、地下街、インフラ設備など、地下空間はさまざまに利用されてきました。地下の開発と利用には、生活の利便性を高める、景観を保全するといった利点があるのも事実です。一方で、工事による地下水脈の破壊、それによる水源枯渇や地盤沈下などにより、住民の暮らしが破壊されています。私たちの目に触れることがなく、不確実な要素が多い「地下」。その開発と利用について考えます。
- 2025年8月15日 発売
- ¥800(税込)
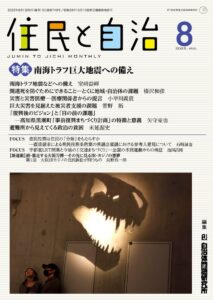
- 2025年8月号
- 南海トラフ巨大地震への備え
- 我が国は今、災害の時代を迎えています。少子高齢化や過疎過密、コミュニティの弱体化など社会の脆弱化が災害対応の困難さをもたらしています。災害が進化すれば防災も進化しなければなりません。この間の巨大災害の教訓に学び、来るべき南海トラフ巨大地震への備えを考えます。
- 2025年7月15日 発売
- ¥800(税込)

- 2025年7月号
- 特集 地下水が危ない―共有財産としての地下水を守るために
- 地下水は地域住民共有の貴重な資源=コモンズです。しかし、地下水の大量汲み上げや地下開発による地下水の枯渇や汚染が各地で問題になっています。本特集は、地下水利用の現状と問題点を概観し、地下水の保全に向けた地域・行政によるガバナンスづくりの課題を考えます。
- 2025年6月15日 発売
- ¥800(税込)

- 2025年6月号
- 特集Ⅰ 自治の力で気候危機対策
特集Ⅱ 巨大データセンターが暮らしを壊す EUの気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」によると、昨年の世界の平均気温が産業革命期前より1.6℃上昇し、2年連続で過去最高を記録しました。気候危機対策はますます喫緊の課題となり、脱炭素に向けてさらなる省エネ・再エネの普及が求められています。
特集Ⅰでは、気候危機対策として地域・自治体に何が求められているのか、紛争を回避しながら地域課題を解決し、地域を発展させる必要性を問います。また、市民参加の力を気候変動対策に生かそうとする取り組みや、再エネで公共交通を支える岩手県宮古市の先進事例を紹介します。
特集Ⅱでは、巨大データセンター建設計画がもたらす地域への悪影響と、それに対して展開されている東京・昭島市、日野市での住民運動を通して、持続可能な社会を支える住民自治と合意形成の難しさを考えます。
- 2025年5月15日 発売
- ¥800(税込)
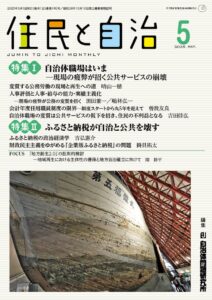
- 2025年5月号
- 特集Ⅰ 自治体職場はいま
―現場の疲弊が招く公共サービスの崩壊
特集Ⅱ ふるさと納税が自治と公共を壊す 特集Ⅰは、「骨太の方針2015」以降、「公的サービスの産業化」として、企業奉仕の行政運営が徹底され、血税が企業の食い物となり、公共サービスの破壊が進んでいます。「全体の奉仕者」(憲法第15条)であるべき自治体職場の現状と課題を明らかにし、住民本位の行政への転換の方向性を考えます。
特集Ⅱでは、寄付額が1兆円を超えるふるさと納税について疑問を投げかけます。納税者が合理性を優先させた結果、多額の税収が無駄遣いされ未来を貧しくする制度はなぜこれほど魅力的なのでしょうか。また、認知度が低い「企業版ふるさと納税」も自治体の民主主義を大きく歪める可能性があります。談合事件も起きた今、どうすべきでしょうか。事例を踏まえながら考えます。
- 2025年4月15日 発売
- ¥800(税込)
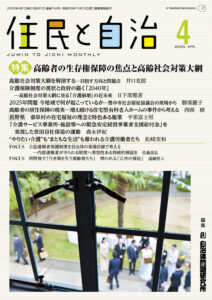
- 2025年4月号
- 特集 高齢者の生存権保障の焦点と高齢社会対策大綱
- 政府は昨年9月、高齢社会対策大綱を6年ぶりに改定しました。「持続可能な介護保険制度」「持続可能な高齢者医療制度」の名の下に、介護保障のますますの縮小や、後期高齢者の医療費負担の拡大などを盛り込みました。また、大綱は「地域共生社会」の名の下に責任を地域に押しつけているかに見えます。しかし、介護事業所の倒産が過去最多を記録するなど「介護崩壊」が現実になっています。また、地域では介護の貧困による介護離職が後を絶ちません。そこで弊誌では、「介護崩壊」や高齢者の孤立、住宅保障など現実が求める生存権保障にフォーカスし、高齢社会対策大綱と現実の乖離にメスを入れます。
- 2025年3月15日 発売
- ¥800(税込)
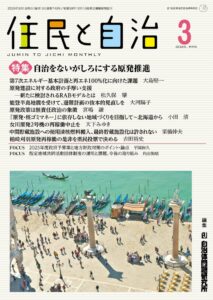
- 2025年3月号
- 特集 自治をないがしろにする原発推進
- 現在、第7次エネルギー基本計画の策定が進められていますが、政府の原発推進姿勢は鮮明になっています。原発再稼働や核ゴミの中間貯蔵施設への搬入が進められることによって、地域住民の不安が高まっています。今号ではこのような情勢を受け、原発をめぐる問題を特集し、国策優先でないがしろにされる地域の暮らしや自治の問題を考えます。
- 2025年2月15日 発売
- ¥800(税込)

- 2025年2月号
- 特集 命を支える水―岐路に立つ水道と自治
- 私たちの暮らし、命にとって欠くことのできない水。常に、気軽に、誰でもが利用できるものととらえていませんか? 現在、水道設備の老朽化や水道職員の減少など、インフラ維持そのものが危ぶまれる事態となっており、水道料金値上げの波も押し寄せています。安定的な公正な水利用のあり方とその危機について、自治体の役割の側面から多角的に考えます。 今年の新春対談は、ゲストにこのほどノーベル平和賞を受賞された日本原水爆被害者団体協議会事務局次長の児玉三智子さんをお迎えしました。広島での被爆体験と差別・偏見の苦しみ、核兵器廃絶に向けての被爆国日本の役割、戦争体験の継承の重要さなどをお話しいただきました。
- 2025年1月15日 発売
- ¥800(税込)

- 2025年1月号
- 特集 能登半島地震からの復旧・復興をめざして―合同研究会シンポジウム報告
- 2024年1月1日に発生した能登半島地震は甚大な被害をもたらし、水道・電気といったライフラインの復旧の遅れや、集落の孤立、避難生活の長期化・広域化などが指摘され、復旧・復興の方向についても議論を呼んでいる。これを受けて6月、自治体問題研究所と自治労連・地方自治問題研究機構は「能登半島地震合同研究会」を発足させ、「災害対応」「原発」「地域経済・復興」「公共交通」など多角的テーマを設定して調査・研究を進めている。本号は、その中間発表の場として設けられた同年9月29日の「能登半島地震合同研究会オンラインシンポジウム」の概要を再録する。
- 2024年12月15日 発売
- ¥800(税込)